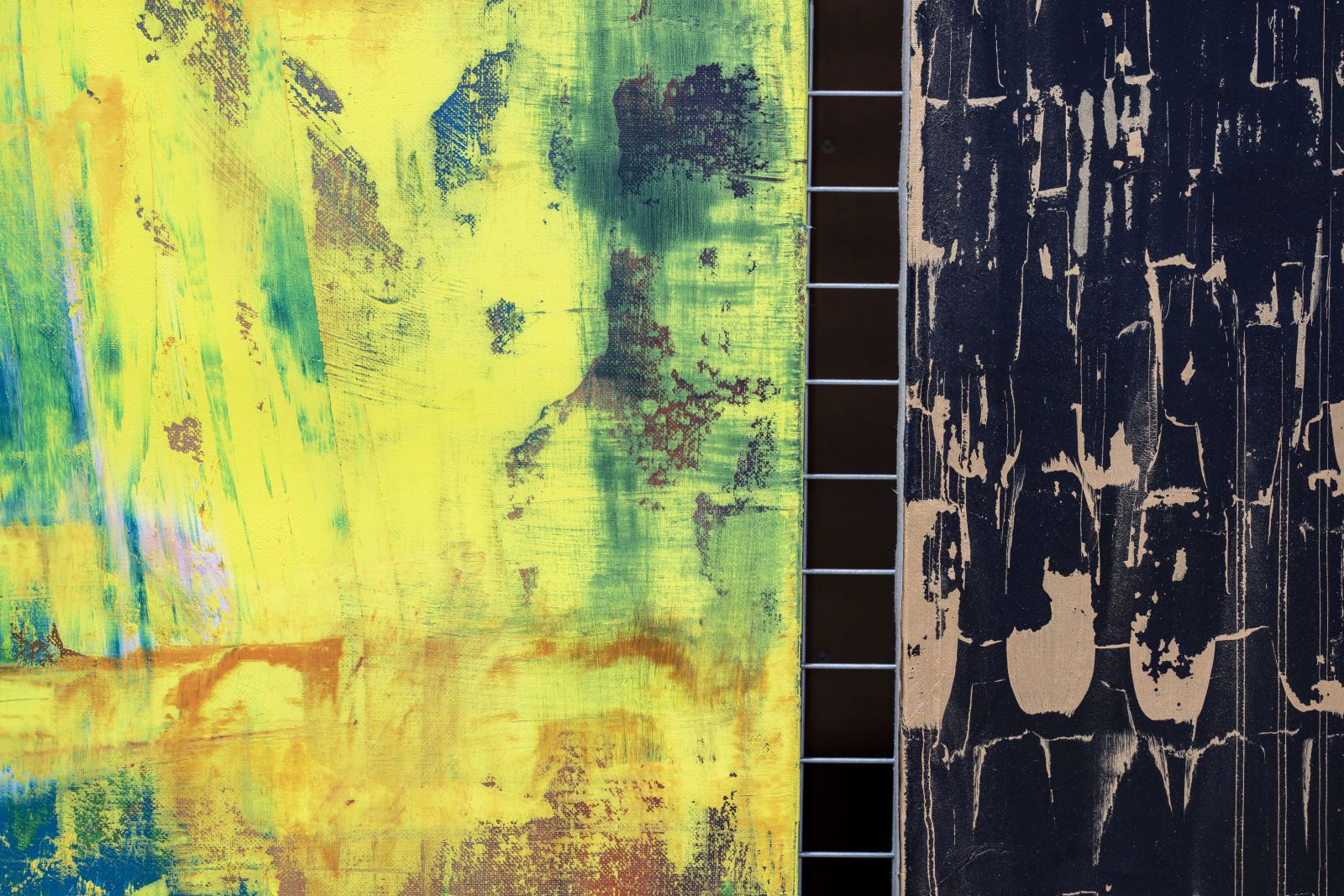多様なアーティストの活躍を後押しする公平なフェア
2018年から開催されている「ARTISTS' FAIR KYOTO」は、今年で早6年目を迎える。すでに京都だけではなく、関東圏を含めた日本のアートシーンの中でも注目を集めるイベントに成長しているといってよい。今年は、3月4日・5日、京都文化博物館 別館、京都新聞ビル 地下 1階に加え、東本願寺の飛地境内地、渉成園(枳殻邸)の3か所をメイン会場とし、4か所のサテライト会場、さらに2022年の「マイナビ ART AWARD」最優秀受賞者Goh Uozumiによる新作個展が重信会館で開催された。
3月2日、開幕に先立ち、出品アーティストの中から優秀作品を選ぶ、「ARTISTS’ FAIR KYOTO 2023 マイナビ ART AWARD」の授賞式がAce Hotel Kyotoで開かれた。ディレクターの椿昇(美術工芸学科教授)をはじめ、飯田志保子(キュレーター)、竹久侑(水戸芸術館現代美術センター学芸員)、中井康之(国立国際美術館学芸課長)の審査により、最優秀賞の宇留野圭に加え、優秀賞の明石雄、八島良子、山西杏奈、山羽春季の受賞が発表された。
椿は、挨拶において、かつてアメリカのトロントで会った日本人アーティストがバザールで自身の作品を売って郊外に家を持ち家族を養っていたエピソードを語り、市民とアートが近い欧米社会の実態を知ったこと、椿の家にも頼山陽や司馬江漢の絵があり、日本にも同じようなたしなみがあったが戦後の住宅事情などによって失われたと語った。椿は、そのようなアートと市民を結ぶ文化を再びつくり、美術・芸術大学に入学した学生が、アーティストとして生計を立てられるようになること、画一的になりがちなグローバルなアートシーンだけではない、多様なアートの生態系をつくることが目標であると述べた。
そのような「夢」を語るアート関係者は今までにも多く存在した。しかし、椿の場合は夢ではなく、時間をかけて1つ1つ実現していっている。まずは、卒業展をアートフェアのようにし、作品を販売するようにしていった。今年は過去最高の売上となったという。その次に、企業に若手のアート作品をレンタルしたり、コーディネートしたりするARTOTHÈQUE(アルトテック)を京都芸術大学を拠点に始めた。その実績とスタッフの育成、行政や企業家とのネットワークを元に開始したのが、「ARTISTS' FAIR KYOTO」である。
特に、目に見える実績は、「ARTISTS' FAIR KYOTO」の参加をきっかけに、実際に、アートを職業にする若手アーティストが増え、それを目指す新しい世代が続々と参入してきていることだろう。今や台風の目の存在となっているが、2018年時点では今日のような盛り上りはなかったといってよい。国際的なアートフェアが活況を呈し、日本でもアートマーケットが勃興し始めているが、「ARTISTS' FAIR KYOTO」では、アーティストが直接フェアを主催し、コレクターと交流して販売することによって熱を帯びるようになったのだ。椿は、アーティスト不在の言説は必要だが、それが本格化されるのは没後のことであり、生きている間は、直接話すことが重要だと指摘する。だから、アートフェアではなく、アーティストフェアなのである。
そして、埋もれていた若いアーティストを引き上げるためのフェアでもある。「ARTISTS' FAIR KYOTO」では、第一線で活躍する15組のアーティストがアドバイザリーボードとなり、アーティストを推薦する仕組みに加え、2019年からは公募制も採用され、広く門戸が開かれている。椿は、アドバイザリーボードのアーティストは、若手アーティストの活動をちゃんと見ていて、それを支援したいと考えていると述べた。今までそれを直接的に後押しする仕組みはあまりなかったが、「ARTISTS' FAIR KYOTO」はその絶好の機会となっているだろう。そのために、アドバイザリーボードも、一つの大学の教員や地域に偏らないように、広く一線で活躍するアーティストが集められている。その意味で、フェア(公平)なフェアであるといってよいだろう。さらに、昨年からギャラリストや批評家との連携によって、リアルタイムの言語化、英語化によって、国際的なシーンへの架け橋にもなるよう布石がうたれている。
創造の原理のたどるさまざまな試み 京都新聞ビル 地下1F
中でも、今年からアドバイザリーボードに参加した、小谷元彦(東京藝術大学准教授)が推薦し、優秀賞を受賞した明石雄はその象徴的なアーティストだろう。明石は、小谷が京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)勤務時代の学生であり、小谷の東京藝術大学への移籍とともに、東京藝術大学大学院に進学した。大学院修了年の2010年に個展を開催し、すでに10年以上のキャリアを持つ。
現在は、出身地である静岡県掛川市を拠点に、絵画や彫刻、あるいはそれらのジャンルやメディウムが未分化な状態にまで微分化し、原始的、あるいは生理的な反応を引き起こす作品を制作している。京都新聞ビル地下1Fに展示されたインスタレーションは、虚像、イリュージョンをテーマにしたモノトーンの絵画と、平面から複数の突起物が噴出している彫刻的絵画・絵画的彫刻といってもよい作品によって構成されていた。
絵画は、ラファエル前派のジョン・エヴァレット・ミレーの《オフィーリア》(1851)の一部や、水に映って反転したシイタケなど、現実と虚像の境目があやうい状態を、砂を混ぜた絵具によってモノトーンで描かれている。《オフィーリア》は、厳密なトレースではなく、見本画像を見ながら描いた模写であり、厳密に見ればデッサンが狂っているとのことだが、確かに《オフィーリア》に見える。それもまた人間の記憶の曖昧さを示すものだが、さらに絵具に砂が混ぜられていることで、照明によって日本画のようなザラツキと反射を伴うと同時に、落ちてゆきそうな危うさを感じる。
いっぽう、前方にある彫刻的絵画・絵画的彫刻は、パネルに土や砂を混ぜたウレタンボンドによって、複数の突起物を突き出している。それらは人間の排泄物のようにも、性器のようにも見えるため、より原始的で生理的な感覚を引き起こされる。それらは意図的に視線の高さになるよう、台座も含めてつくられているため、自立した彫刻とも捉えることができる。もともとは、チューブから出る絵具のイメージであり初期はカラフルな作品もあったとのことだが、顔料をたどればオーカーのような土や砂があることから、素材そのものである砂を混ぜていった。さらに、近作では素材に石を使ったり、支柱に掛川の砂浜から拾った枝を使うなど、より原始的な素材を使用している。自身の環境や素材と対話しながら、絵画や彫刻という様式に捉われず、自身の感覚の中にある基層を取り出そうとしているといえるだろう。その探求が流行にとらわれない普遍的なものであるからこそ、今回、選ばれたといえる。そのような地道な制作も実を結ぶことを、「ARTISTS' FAIR KYOTO」では示された。
いっぽう、同じく砂を扱いながら、最先端の試みに取り組んだのが、R E M Aだ。R E M Aは、2023年3月末から2024年3月末までの約1年間、大阪のグランフロント大阪で設置される約4m弱にも及ぶ、自身をモデルにした、屋外大型彫刻の1/5模型を出品した。それは砂を素材にして、3Dプリンターで成形されており、今までにない手法として注目されている。
R E M Aは、ポートレートやジェンダーをテーマにした作家であるが、京都芸術大学の大学院を修了し、現在は京都芸術大学でサポートスタッフをしながら作家活動を続けている。学生時代からウルトラファクトリー主催の「ULTRA GIRLS COLLECTION」展、服部浩之(キュレーター、東京藝術大学准教授、東北芸術工科大学客員教授)がキュレーションしたKUA ANNUAL 2021「irregular reports:いびつな報告群と希望の兆し」展、多和田有希(美術工芸学科准教授)と後藤繁雄(大学院芸術研究科教授)が担当した「写真は変成する2 BLeeDinG eDgE on PoST/pHotOgRapHy」展などに相次いで出品してきた。



今回は、学部時代に制作した巨大なポートレートの平面作品から、立体作品へと展開させた。しばらくの間、葉や木材にドローイングした写真作品など、自身の内面を表現する試みを行ってきたが、今回は再びポートレートに挑戦している。ただし、平面と違って、つけ睫毛やアイライン、編み込まれた髪など複雑な形状を、彫像として表現するには苦労したという。その際、一番参考にしたのは、ミケランジェロの彫刻だという。ダビデ像の目の表現などにみられる、凹凸をつくって陰影によって表情を生み出す方法を採用した。最新の技法を使いながら、古典技法の到達点を学ぶ機会にもなったという。作品は、鋼管によって組まれた台座の上に立つが、ギリシア建築のオーダーのようにも見える。また、砂でつくられていることもあって、古代エジプトの砂像のようにもみえるところが興味深い。
2022年に大学院芸術研究科美術工芸領域染織テキスタイル分野を修了した長田綾美も、在学中から多くの京都芸術大学の展覧会に選ばれている。学生選抜展「KUA ANNUAL」は、2021年の「irregular reports いびつな報告群と希望の兆し」展、2022年の「in Cm | ゴースト、迷宮、そして多元宇宙」展の2年連続で選ばれ、2022年の作品は、大学院修了展で大学院賞を受賞している。ブルーシートや不織布などの既製品を、石やエアガンの玉などを「絞り」の技法で括り付けていき、固定観念で見られていた既製品のイメージを、手織りによって変容させる作品を制作している。
大学院を修了して、自宅の部屋をアトリエにし、ライフワークとして集めていた特徴的な柄の既製品の生地を、絞りによって中央部で括り付け、模様を変容させた布を、パッチワークのように縫い合わせて、巨大な一枚の布を制作した。絞り染めは、布の一部を縛り、部分的に染料が染み込まないようにして、模様をつくる技法であるが、すでに模様のある布を、絞ることによって別の模様にするという、逆転の発想といえるだろう。大学や大学院を修了した後、どのように制作環境を確保し、継続していくかは難しいが、長田は極めてシンプルな方法で、継続する可能性を示したといえる。
あるいは、大学院在学中の小西葵と山口京将からなるアートユニット、モフモフ・コレクティブは、それぞれ「もふもふ」する毛深い布をつかって、人間ではない生命体のような作品を制作している。昨年、瀬戸内国際芸術祭2022県内周遊事業 「おいでまい祝祭2022〜心がつながる街ごとアート〜」において、ヤノベケンジ(美術工芸学科教授)と共に、大がかりな作品展示を成功させている。
今回も、作品点数を増やし、巨大な彫刻のインスタレーションを展開した。山口は、奇妙な顔をした不思議な生命体を、小学生の時に母親から「人面鳥」がいると嘘をつかれたことから、永遠に会えない生命体のイメージを膨らまし、独特な形をつくったという。小西は、自らの生み出したキャラクターを着るパフォーマンスも行う。まさに「嘘から出た実」ともいえるが、実体のなかったイメージをつくって、現実を変えるのもアーティストの役割といってよいだろう。
2013年に京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)大学院を修了した前谷開は、すでにキャリアのある作家であるが、今回は公募によって参加した。「KUA ANNUAL」の前身である「ULTRA AWARD 2015」に選出され、卒業後はHAPSスタジオや共同スタジオ 山中suplexに所属し、多くの展覧会に参加してきた。
さまざまな環境に身を置く、自身のポートレート写真を主なメディウムとし、近年では風景(scape)をテーマに、自分の身体によって知覚した風景を再構成し、新たな風景を現出させるインスタレーションを行っている。今回は、京都新聞ビル地下1Fの一番奥にあるスペースに、写真、映像、、京都府の最北端に位置する経ヶ岬の灯台を撮影した映像のプロジェクション、京丹後地方で生産される縮緬織の生地で制作された特注の合羽(cape)などを使い、レジデンスで滞在した丹後半島の風景を再構成している。それらは、前谷が見た風景、風景から見られた前谷を行き来する視線の循環をもたらし、鑑賞者に対しても、その一端が開かれていく。ベラスケスの《ラス・メニーナス》(1656)のような視線と鏡像の循環を、実際の空間で行う新たな風景描写といってよいだろう。
メディアの複製と転換、変容から生成される絵画群 京都文化博物館 別館
いっぽう、京都文化博物館 別館は、今年は1階だけの展示となり、例年に比べて見やすくなっている。なかでも、入口一番手前に展示されている川村摩那(大学院芸術研究科美術工芸領域油画専攻)は、今までにはあまり見られないキャリアを経ていて興味深い。川村は、早稲田大学の文学部で近代文学を研究した後、IT企業に就職し、数年間働いてから、京都芸術大学の大学院に進学した。大学時代は志賀直哉や夏目漱石などをテーマに、特に鉄道のような交通網の発達が、文学に与えた影響を研究していたという。確かに、近代絵画においても、印象派以降、鉄道による移動、知覚の変容が大きな影響を及ぼしている。それらの経験を元に、文学や古典を自身の方法で解釈し、絵画に変換して描いているという。
特に、夏目漱石などは、作中にさまざまな絵画が登場し、イギリス留学中を含めて漱石が見たさまざまな絵画が、夏目文学の中に通奏低音のように流れている。2013年には、東京藝術大学大学美術館 で「夏目漱石の美術世界展」が開催され、小説の中に登場するさまざまな絵画が紹介された。ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー、ダンテ・ガブリエル・ロセッティ、ブリトン・リヴィエラー、ジョン・ウィリアム・ウォーターハウスなど、漱石が近代小説を構築する上で、イギリス絵画が大きな影響があったことは見逃せないだろう。
川村の方法は、文学や古典、戯曲の中にある絵画性を取り出したものだといえるが、その際、言葉が指し示す意味をFocus(焦点的印象、観念)、行間から感じるものをfeeling(感覚、情緒)と解釈し、輪郭や色彩、絵具に転換している。展示された大型の作品は、漱石の『文学論』、『古事記』、サミュエル・ベケット、宮沢賢治『銀河鉄道の夜』を解釈した絵画である。その中には、全体のイメージもあれば、個別のシーンを取り出したものもあり、具象と抽象の割合がモチーフによって変わっている。特にベケットの不条理劇を解釈した、1+1を反覆しながら輪郭が崩れたり、ずれていく作品など、文字や数字の意味が、形だけを残して内容が変容したり、表現のディテイルは崩れて構造だけが残るといった、物語や小説、戯曲の再演の問題が絵画に表されている。
また、文学と絵画という近代化の過程で互いに純化し、直接的に交わらないと思われていたものを、明治以前の文人画のように、書画が一体となった新たな融合も視野に入れており、まだまだ可能性を感じる作品群であろう。春からは若手現代アーティストの住むコミュニティ型アートホテル&アートホステル「河岸ホテル」にアトリエを構え、アーティストとして活動していくという。これから新たなシーンを創っていくことが期待される。
大澤巴瑠は、コピーによる複製の過程で生まれたノイズ、バグをモチーフにしているアーティストである。2022年には、服部浩之のキュレーションによる「in Cm | ゴースト、迷宮、多元宇宙」展に選出され、2022年3月、大学院芸術研究科美術工芸領域油画科を修了した。その際、猫のドローイングを複製していき、何十枚と歪ませた中から、猫かどうか判別がつかない状態のものを選んで、コピーを原画にして絵画に仕上げた。
コロナ禍の中で、「複製」されたものが、コピーの過程でミスを起こし、変容していくという事実は、私たちにとって馴染み深くなっただろう。新型コロナウイルスが、何度も大きな変異と小さな変異を繰り返し、感染力の強い変異株によって既存の株が塗り替えられることを、自分の生命に関わる問題として見てきた。
それはウイルスにとっても、生物にとっても重要な働きであり、より環境に適応した変異種が残っていく。それが時に「進化」とも言われるわけである。大澤は、コピーのミスを「バグ」と言い、オリジナルと複製、デジタルとアナログの価値転換として扱っているが、私たちの生命にとって本質的なテーマであるといってよい。
大澤は、今回、猫のようなすでに先入観のある記号的なイメージを使わず、複合機に直接、墨でドローイングをして、それを原画にして、絵画に仕上げた。キャンバスには銀箔が貼られ、黒の部分は墨で塗られている。黒の輪郭には、アクリル絵具で赤、黄、青が縁取られ、混色の原理が示唆されている。それによって、より黒は浮き上がったような非物質的なデジタルイメージに見えるが、それらはすべて大澤による「手描き」である。銀箔は、スキャニングされる走査線、ライティングをイメージしているとのことだが、墨の痕跡と相まって、抽象的な書に見えるところもポイントだろう。そこに意味はなく、複製とデジタル・アナログの変換のプロセスが示されている。しかし、複製と変異の情報が物質化、血肉化しているのが私たちの身体、生命であり、ある種の生命のメタファーになっているといえる。大学院を経て、大澤のテーマと表現がより明確な輪郭を帯びたといえる。
山中雪乃は、2023年3月に京都芸術大学大学院芸術研究科美術工芸領域油画専攻を修了するが、2021 年の「ARTISTS’ FAIR KYOTO 2021」でも展示している。2回目となる今年は、京都文化博物館で個人で選ばれている他、2019年、同級生3人により結成されたアートユニット「Painter gals carandsex」としても選出され、京都新聞ビルでパフォーマンスが行われた。
山中は、知人や人形をモデルに、存在や認識の不確かさを表現しているという。グレー系の無地の背景に、はっきり認識できる顔や手が描かれているが、滑っとした光沢のある質感で描かれたり、ほとんど描かれていない余白や筆触や筆致が残った部分が、奇妙に溶け合って混在している。詳細に描かれていないのに、リアルに感じてしまうのは、人間の知覚が、余白の不足している部分を、補完してしまうからだろう。その部分は、見る人間の脳の中にだけにある仮想的なリアルである。
映画『ターミネーター2』に登場する液体金属のように、今にも溶け落ちていきそうな表現によって、変容していく過程を見ているような感覚にもなる。存在というのは、私たちの知覚の中で立ち現れる虚構であることが描かれているため、見ている方も不安になるのだろう。いっぽう、後ろ向きに描かれた人形などは、それが何を描いているのか、把握しようとしてしまう。記憶の中でいろんなものを参照してもたどり着かない不安感もまた、存在の不確かさを感じるものだ。そのように、見ている以上に見てしまう、見えているのに理解できない、といった存在と認識をめぐって、私たちの脳のスクリーンこそが山中のカンヴァスといえるかもしれない。
アートと社会を結び直す京都の役割
昨年、アドバイザリーボードのアーティストの作品は、清水寺で展示されたが、今年は、東本願寺の飛地境内地、渉成園で展示された。また、渉成園の中の閬風亭は、若手アーティストの会場にもなった。
渉成園(枳殻邸)は、1641(寛永18)年に三代将軍、徳川家光から約1万坪が寄進され、現在も200メートル四方、面積3.4ヘクタールに及ぶ広大な庭園を擁している。武将・文人であった、石川丈山が作庭した、広大な印月池が残り、1936(昭和11)年には文人趣味にあふれる仏寺庭園として国の名勝に指定された。
印月池の周囲には、さまざまな草庵が立てられており、それらに14組の第一線で活躍するアーティストが趣向を凝らして設置している。大玄関の軒先には、ヤノベケンジの《SHIP’S CAT》シリーズの巨大な眠り猫《SHIP'S CAT(Mofumofu22)》(2022)が出迎え、大玄関にはYottaの《花子》のシリーズが展示された。2011年から各地で展示されている《花子》(2011-)はバルーン製なので、屋外に置くと傷みや汚れも出てくるので、つくり直されている。今回は、過去の《花子》を切り取り、桐のパネルに組み込んで、平面作品としても展示されたというわけだ。
新しくなった全長12メートルのバルーン製のこけし像《花子》は、今年は東本願寺門前に涅槃像として設置され、「ARTISTS' FAIR KYOTO」開幕前からSNSで話題なっていた。さらに会期中には、ヤノベが、少し前に発表した電気自動車型の彫刻《SHIP’S CAT(Speeder》(2023)も、ヤノベ自身が運転しながら各会場を回って花を添えた。
おはようございます。
— ヤノベケンジ (@yanobekenji) March 3, 2023
本日4日土曜日の気まぐれ《SHIP'S CAT(Speeder)》ドライブの予定です。
14時 京都芸術大学出発
14時半〜15時 京都新聞社AFK会場
15時半〜16時 東本願寺涉成園AFK会場
16時半〜17時 ホテルアンテルーム京都 SSS展会場
17時 帰宅whttps://t.co/q5tRRc1cMk pic.twitter.com/dvmnuMiytu
その他、臨池亭に展示された、大庭大介(大学院芸術研究科准教授)や池田光弘(美術工芸学科准教授)の作品は、季節や時間、日の光の変化と共に作品を楽しむ日本美術の在り方の今日的な提示となっていた。蘆菴では、自然の石にメッキを塗装した鬼頭健吾(大学院芸術研究科教授)もまた、自然と人工のコントラスト、輪郭と形を前景化させ、2階の床の間に展示した名和晃平(大学院芸術研究科教授)は、立体のモチーフを漆黒の油絵具やビロードで覆い、日本の美学である陰影のさらに奥にまで作品を拡張した。
さらに、傍花閣では、椿昇が3Dプリンターで生成する「バベルの塔」を展示した。3Dプリンターの台座は、迷彩柄で覆われており、これが昨年冬から始まったロシアによるウクライナ侵攻と、「バベルの塔」のように未だに分かり合えず、対立を繰り返す人間の業のメタファーであることは言うまでもない。作品タイトルとなっている、「Why the Future Doesn't Need Us」とは、2000 年 4 月にコンピューター科学者、ビル・ジョイが、Wired誌に掲載したエッセイのタイトルである。そこでビルは、「ロボット工学、遺伝子工学、ナノテクノロジーといった21世紀の強力なテクノロジーは、人類を絶滅させる恐れがある」と主張した。ビルの、未来の技術に対する警鐘は、「技術的特異点(シンギュラリティ)」を説いた未来学者レイ・カーツワイルとの議論から生まれたものであるという。
2045年、人工知能が人間の知性を超えると言われていたが、OpenAIのチャットロボット、ChatGPTの登場は、その未来予測がもっと早く、人間社会に大きな変革を及ぼすことを示したといえる。その時、アートに何ができるのか?自然と人間の調和の美学をつくりだした、1200年都市、京都から何を発信できるのか?アートと生活、市民が再びどのように結びついていけるのか。渉成園はそれを考える最適な場所だろう。
ARTISTS' FAIR KYOTO 2023のリードパートナーである株式会社マイナビ執行役員である落合和之氏は、授賞式のあいさつで、アート思考はビジネス業界でもますます注目を浴びるようになっており、アーティストの創造力や洞察力が社会から必要とされていると述べていた。「ARTISTS' FAIR KYOTO」というアーティストの挑戦は、危機的な状況にあるこれからの社会とっても重要になるのではないか。
(取材・文:三木学)
京都芸術大学 Newsletter
京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。
-
京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts
所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス
連絡先: 075-791-9112
E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp