
文:北桂樹
1977年東京都生まれ、2023年に京都芸術大学芸術研究科芸術専攻を修了。博士(学術)。「POST/PHOTOGRAPHY(ポスト・フォトグラフィ)」をテーマに、現代写真の変容を「写真変異株」として捉え、写真というメディアの拡張について学術研究に取り組んでいる。主な研究対象はトーマス・ルフ、ワリード・ベシュティなど。
本レビューについて
本稿は、デジタル化以降、急速に進む写真というメディアの状況の中、現代写真研究に照らして考えた時、若いアーティストたちのまだ「名づけ得ぬ表現」を如何なる形で拡張し得る「写真変異株」であると捉えることが可能なのかという点をスタートにしている。そこから、本展のキュレーションのテーマである「インタープレイ」が写真というメディアの境界における「共生進化」の場、つまり「POST/PHOTOGRAPHY(ポスト・フォトグラフィ)」という新種の生成を目指したものであったことを明らかにすることに重点を置き論を進めている。
3回目となるこの展覧会は、写真というメディアの急速な変化、さらにはその存在論をラディカルに問う視覚体験をわたしたちに毎回突きつけるものである。その意味において、国内ではほかに類を見ない展覧会といって間違いない。
コロナ禍の最中の2021年に初めて開催された本展は「真実性」を放棄し、全方位へと境界を横断し、変成をさせた写真表現をラインナップとした第一回の「MUTANT(S) on POST/PHOTOGRAPHY」、様々な表現渦巻く混沌の中、境界線で起こる分裂生成によって何かが生まれる予感を感じさせた第二回の「BLeeDinG eDgE on PoST/pHotOgRapHy」を経て、第三回となる今回はキュレーター後藤繁雄、多和田有希のふたりに加え、川島崇志(東京工芸大学)、髙橋耕平(京都芸術大学)を加えた形で、京都芸術大学/大学院(写真・映像)と東京工芸大学との共同選抜展となった。
写真というメディアのデジタル化は単に出力されるメディウムの構造を銀のノイズからピクセルへと置き換える以上の変化を写真というメディアにもたらした。デジタル化は「入力―変換―出力」という写真の生成段階のすべての領域において拡張を可能にし、ヴィレム・フルッサーがチェスのゲームに例えた写真の可能性を爆発的に複雑なものとした。全方面に拡張する写真はウイルスのようにさまざまな変異株を生み出し、写真誕生のころ以来となる非常にエキサイティングな時代へと突入している。写真はもはやこれまでの写真のままではいられない。
本展、「写真は変成する3 INTERPLAY on POST/PHOTOGRAPHY」は「インタープレイ/相互に作用するということ」をキュレーションテーマとし、大学間の交流はもちろん、メディア領域の臨界点、若きアーティスト同士のそれぞれの表現間で起こる相互作用を加速させ「写真変異株」を共生進化の中に生み出そうとする実験的なショーケースとなっている。
筆者は「POST/PHOTOGRAPHY」というものを「写真ウイルス」に喩え、その変異による「写真変異株」という概念として検討することで、これからの写真を考える手がかりとした。写真の拡張は従来の写真というメディアそのものの領域を拡張する動きに加え、直接的に繋がりがなくても新たな視覚体験によって世界を構造化する「写真性」をもった表現によって突然変異として別の場所に現れる。さらには従来の写真表現の延長線上にある展示性や言語との相互関係などを含めた表現など、あらゆる場面で写真というメディアは変容し、拡張し続ける。いまや写真はひとつの写真術の中、イメージ同士の比較では理解ができないところまで来ている。必要とされるのはアーティストが行う、イメージとオブジェクトの両方を生成する写真術の開発とその時に行われる選択とアイディアへの理解となる。本展に提示された表現のいくつかを紹介することでその理解を進めたい。
世界を平面化し、オブジェクトとする写真の本質


道場美秋《δ(x , y)》
大学ラウンジから天井が開けた会場に入ってすぐに目につくのは道場美秋の作品《δ(x , y)》だ。作品は高さ2m、幅1m、奥行き30cmほどの木枠の表裏の両面にモノクロプリント2枚が貼られ、自立している構造物による作品群である。
イメージはすべて建物内の壁2面と床面が交わる部屋の隅っこを同じように撮影したものである。さまざまな部屋で撮影をしてはいるものの、一般的に建物の部屋が四角い構造をしているため、イメージはどれも同じように、三つの面、三つの辺が交わるものとなる。すべての建物内における撮影を同じようにしていること、余計なモノが画面内に入り込まないようにし、立体感を作り出すパースペクティブが可能な限り排除され、坦々とイメージが繰り返されていることによって、これらのイメージはすべて、アルファベットの「Y」を逆さまにした3つの線の交わり「⅄」のバリエーションへと変換が行われる。長方形の印画紙は、二つの台形とひとつの五角形に分けたひとつの平面、つまり印画紙サイズの一枚の平面であることへと還元される。これによって、三次元空間の奥行きを圧縮し、二次元平面へと変換する写真の機能そのものを強調する装置として働く。
次に、道場の作品はイメージとして存在するのではなく、自立した立方体の構造物であることに目を向けると、この構造物の2面に貼られたプリントとプリントとの間から真っ白な印画紙の裏側を見ることが可能であり、なんなら、内側に入り込むことが可能となっており、それぞれがひとつの小さな部屋となっている。建物の壁の一部を撮影したイメージであるプリントはふたたび別の形でひとつの壁へと回帰させられており、このオブジェクトのある1面、つまりひとつの平面であることをより強調する。
さらに、作品タイトルの《δ(x , y)》に使われている関数「δ(x , y)」は2つの変数を持ったディラックのデルタ関数を意味するのではないかと考えられ、ある二次元平面上の点(0,0)において「スパイク」(非常に大きな値)を示す(適切な枠組みの中では意味を持つ)超関数である。つまり、「δ(x , y)」は二次元平面上のある点に関わる。このことは、この作品が平面に関わる問題であることをまた別のレベルで示している。
建物内の部屋の角という対象は、X軸、Y軸、Z軸という3辺が交わる極めて三次元的なモチーフでありながらも撮影によって切り取られ、立体構造物の一面として示されることで、二次元的平面であるという事実と入れ子となる。《δ(x , y)》は作品のイメージ、オブジェクト、タイトルと写真作品を構成する全ての要素を活用し、鑑賞者の中で写真における三次元の立体空間と二次元の平面というふたつの空間の「入れ子構造」の反復を作り出すことに成功している。世界は写真に撮られることで、二次元化、オブジェクト化され、世界とは別のモノになるのである。
写真がもはや、イメージだけの問題に関わるものではなく、イメージとオブジェクト、さらには写真が現象ではなく、概念を指し示す。つまり、テキストをメタ化するという特徴を考えた時、この作品はこの先の作品とわたしたち鑑賞者がどう関わるのか、どう読み解く姿勢でいるべきなのかということに関して、あるひとつの基準値をつくる。その意味でもオープニングを飾るに相応しい作品であった。
身体イメージを変化させ、世界の変化を追い付かせる。

中川桃子《Heavy drag》
少し会場の入口から入ったところにある壁面に巨大な壁画のように展示された作品は中川桃子の《Heavy drag》である。一つの大きな白い壁面から部分的には飛び出すように設置された写真作品は、一見すると会場地面から伸びた大木のようでもある。
作品を構成するものは、人間の身体(ステートメントから察するには作家自身か?)の写真だ。その写真のイメージはデジタル処理のマニピュレーションによって大きく変形させられた上で、それぞれ身体のイメージを手や足、背中、鼻、耳、唇などパーツごとに切り抜き、壁一面にコラージュ、その一部に女性ものの黒い下着だけが現実世界との接点として提示されたかのような作品である。切り抜かれた身体はどれも単独で存在はせず、つなぎ合わされてひとつの身体を再構成していることから、バラバラな身体というよりは「ひとつの身体の変形」と考える方がよいようにも思える。
イメージのさまざまな場所に多くの釘が直接打ち込まれており、透明メディウムがあちこちに乱暴に塗りたくられている。これらは作品を壁面にひとつの身体として留めるためのもののようでもあり、身体そのものを汚し、傷つけているというようにも見え、二律背反するパラドックスを鑑賞者の中に湧き上がらせる。ステートメントや世代のことを考えると、網の目状に壁一面に広がるその様はリゾームのようにも思え、中心となる体幹を持たない身体によって、逃走の線を引くのだろうと思ってしまう。まさに身体を変化させて痛みを回避するのだろう。
《Heavy drag》を前にして考えたことは、そういった現実の痛みに対して、身体のかたちを変えるという彼女たちの選択だ。
コロナ禍において、人々が直接会えない日常のコミュニケーションを支えたのはZoomやFacetime、LINE電話などのビデオ通話であった。「リアルで会うのははじめてですね」という挨拶がここへきて繰り返される毎日である。さらにはTikTokやInstagramなどSNSアプリの画像処理、加工の進化は凄まじく、常に被写体の顔を認識し、目を大きくし、肌をキレイに明るくするなどその精度は格段に上がっている。そこに加工があることはわかったとしてもどの程度の加工が行われているのかはもはや判断できない。スクリーンは現代における鏡として機能している。
マーシャル・マクルーハンが発した「メディアはメッセージである」という有名な警句の本質はメディア使用の変化によってわたしたちの身体性が変化をするということであった。誰が言っていたのかに関して失念してしまったが、写真はわたしたちに写真自身が捉えられている「遠近法」という世界との触れ方を常に教育し続けている。そのことによってかつてあったさまざまなものを「見る」方法はなくなってしまったという。さらには、映画やドラマにおける「フォーカス送り」という遠景と近景をフォーカスで視線誘導する技術は、わたしたちの「見る」をシミュレートし、視線を誘導する。実際はフォーカスがあった方を見ているのではなく、見ていたものがただボケただけで、それを「見る」だと思い込まされていく。
《Heavy drag》はお風呂場にある鏡の上の無数の水滴を通した世界のようなものだ。全身が映った鏡に水滴が付くと、その水滴の中には変形させられた無数の自分が映し出される。水滴の自分を見ている時、変形をしていない全身の自分は見えなくなっている。自分自身を変化させることとは元の形をなくすことだ。そのために、イメージを現実に先行させているということが非常に興味深い。イメージによって、新たな現実を創造しているということになるのだ。人は見たいものしかみない。そして、見ている世界によって世界は変わるのだ。
近年、イメージ側の身体を変化させる表現を目にする機会が増えているように思える。現実が物質世界だけではないということが徐々にアタリマエになってきたことによって、それに反応するアーティストが出てきたということなのだろうかと思う。別のアプローチで自身の身体とその境界を克服しようとした作品が菊池詩織の《野生の呼び声》である。


菊池詩織《野生の呼び声》
菊池詩織《野生の呼び声》は、白い背景、白いシーツのベッドの上に四つん這いの姿勢の女性を撮った横長の写真作品と、筆を並置した展示となっていた。写真作品について、それがただのヌード作品でないのは、アーティストがそこに無数の自身の髪の毛を植毛し、一見すると毛むくじゃらの動物の写真のようにも見えることだ。
写真の頭頂部の髪の部分にも髪は植毛されているのだが、ぱっと見はイメージとしての髪の毛と植毛された髪の毛との境界がはっきりはしないほど、しっかりと植毛されている。そのまま首、肩、背中から足の先までみっちりと髪の毛によって全身が埋め尽くされている。菊池の問題意識は地球上における人間という動物の特権的な立場に対する疑問である。
かつては人間も世界の一部であったにもかかわらず、言語の発明、道具の使用、メディアの発明、産業革命と段階を経ながら人間はいつの間にか様々な他者を支配する側になっている。「人新世」という人の活動が地球規模で影響を及ぼすという地質年代の言葉が生まれて久しい。一方で、「わたしたち」ということをどこまで拡張するのかという問いは、人間中心主義を脱却するときに考えなくてはならない大きな問題であろう。人間だけが「わたしたち」なのだろうか?
動物を人間側に寄せることもひとつの方法であろうかと思うが、菊池がとった方法は自分自身が動物側へ寄って、見せることだ。ダナ・ハラウェイの『伴侶種宣言』にはじまるマルチスピーシーズの考え方を下敷きにし、人間が西洋近代以降に一方的に引いた主体客体のような二元論の境界線を自身の身体を変化させ、イメージによって語る物語で乗り越える。
写真に写ったイメージの自身に丁寧に施された仕事によって、作品は不気味なほどのリアリティをもって、鑑賞者であるわたしたちに、「わたしたち」の境界線がそれほどまでにはっきりとはないことを見せてくる。イメージを変化させることがもたらす説得力は言語的な理解を超える。これもイメージを先行させることで、世界を変化させるひとつの手段なのだろうという印象を受ける。
彼女たちの表現を見ていると、写真はかつての「真実」を担保するものではなく、現実を拡張し、変化させ得る物語を語る手段となっていっていることがわかる。
「テクストとイメージ」をめぐる課題
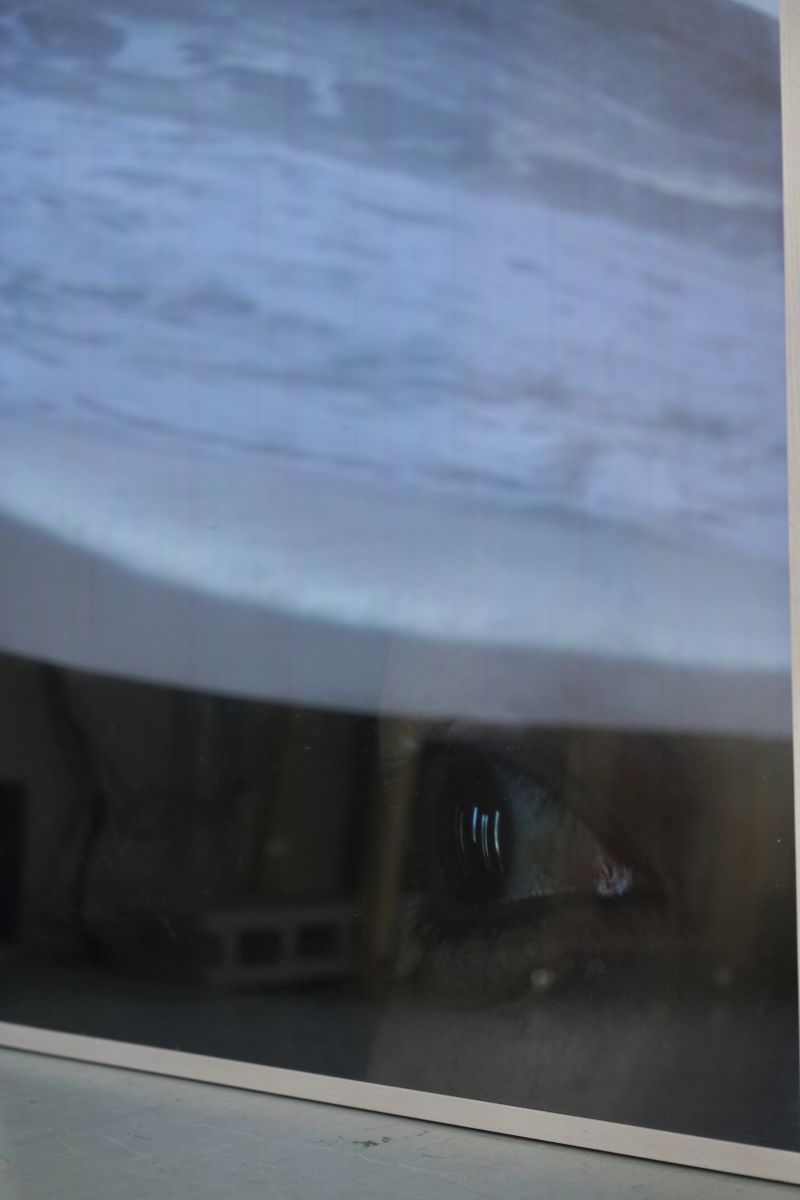
原田一樹《波は身体に押し寄せているか》
別の形で自身の身体(呼吸)と世界との関係を探求し、可視化して見せているのが原田の作品《波は身体に押し寄せているか》であった。ギャルリ・オーブ奥の暗室を利用して提示された、プロジェクションされたシングルチャンネルの映像作品には繰り返し押し寄せる波の映像と自身の呼吸の音がシンクロされている。さらに、正方形に近い一辺100cmほどのフレームに額装されたプリント作品が3点という組み合わせによって構成されたインスタレーションである。
「呼吸」と「波の波長」というものの関係から、人間の身体と地球のエコシステム、さらには波を起こさせることに関連する月との関係へと思いを巡らせることが本作品の狙いとなっている。
たしか、この作品は京都芸術大学写真・映像コースの3回生時の課題「旅と文学」で、2022年12月に京都のギャラリーで展示された作品を原型として本作品に発展させたものであったと思う。本課題についての詳細は詳しくはないので省かせてもらうが、文学作品の中の一文を発展させて作品へと昇華させていたはずだ。
ヴィレム・フルッサーは「写真」が目の前の「現象」を指し示すわけではなく、「概念」を指し示すとする。そのことにいち早く気がついていたコンセプチュアル・アートのアーティストたちは自身の「概念」を示すのに「写真」という手段を選んだ。さらには写真である「テクノ画像」は世界の第3段階の抽象であり、テキストのメタテキストとして機能するということを考えると、目の前にある波の映像と月の写真、人物の目の写真、砂浜の写真が指し示すものが、映し出されているものそのものではなく、彼が選んだ文学の中の「テキスト」であるということを思わせ、興味深い。文学という他者の思考をテキスト化したメディアを映像化させるということが持つ意味は写真というものの存在意義を「真実性」や「イメージ」というものから遠ざけ、原田が呼吸と波の反復の親和性から月へと思考を発展させたように、連想的になる。科学とはちがった方法、つまりデカルト的な考え方とは違った方法で世界とわたしたちの関係を考える物語的な方法に写真や映像が関与している。

成瀬凛《受動と抵抗を繰り返す、あるいは》
原田と同じく、この「旅と文学」を発展させる形で作品を提示していたのが、成瀬凛の《受動と抵抗を繰り返す、あるいは》である。成瀬は服というものを人間の皮膚(を拡張した器官)として考える。人間と外界との関係、つまり認知に関わる問題をもとに、その服を着て、脱ぎ、洗濯(漂白)という日常的な行為のもつ意味を再検討・再構築する。作品は様々な衣類がいくつも宙吊りにされ、不安定に展示されたオブジェである。吊るされている衣類は、バラバラに切り刻まれたものがつなぎ合わされることで、ふたたび一つの服として見えるようになっており、それらは過度に漂白されることで、どれも白から微妙に肌色がかった色のものとなっている。このことは一層服が皮膚という感覚器官の外部化であることをほのめかす。天井からワイヤーで衣類は吊るされているのだが、衣類はひとつずつ天井から吊るされているのではなく、片手は天井からのワイヤー、もう一方が他の衣類と繋がっているといったように連動してつるされており、どこか一つの部分が崩壊することで、全体が崩壊するような形で不安定に天井から吊るされている。ここには複雑かつ面倒でもある現実世界の人間関係が反映されているようにも思える。
たしか、本作の元となった文学が川端康成の『舞姫』であったかと思う。元バレリーナの母と娘を中心とした一家が内部崩壊する様子が描かれた物語で、人間の美や孤独を探求した作品と言われている。
成瀬の作品も原田と同様に、他者の思考をスタートにしてイメージ化を進めたものとなる。物語(とその中の一文)の選択が実質的なインプットとなっており、アーティストの思考とシンクロされながら、変換され、オブジェクトとして出力される。漂白された服そのものが、外界からの影響そのものを受け取る撮像素子であり、支持体であることなど、その点において、本作品も「写真性」によって拡張された写真作品とも言えるかと思うが、テクストのメタメディアという点がむしろ本作のテーマである「インタープレイ」というテーマが拡張する部分と考えたほうが効果的なように思える。
インタープレイを象徴し、会場内を航行・交流する

高尾岳央《Sails》
今回の展覧会のキュレーションテーマ「インタープレイ/相互に作用するということ」を象徴するひとつの作品が高尾の《Sails》である。高尾の作品はエアブラシによって描かれた「ペイント」作品をマウントした木枠の構造にタイヤがついた構造体である。
イメージだけをみれば完全に「ペイント」そのものであり「写真」であるという要素はそこにはない。作品タイトルである《Sails》は帆船の帆を意味する。これは高尾が制作するエアブラシという道具に由来している。エアブラシはストリートアートのグラフティなどでも使われる道具なのだが、筆を使って描くペイントと違い、支持体であるキャンバスはエアブラシの噴射する風を受けることによって着彩され、描かれるのである。高尾はこの点に着目し、絵画を構成する要素と行為とを分解、再構成することで、ペイントをユニークなオブジェクトへと再構築する。
タイヤのついた構造体は作品を会場のゾーニングへの固定からも解放し、展覧会という海上(会場)を自由に航海する。メディアとメディアという境界のみならず、作品と作品という境界を軽々と乗り越え、交流する。かつてはフィルムを、デジタル化以降は撮像素子を入力面という装置とし、光をそこへ取り込み二次元へと変換してきたのがカメラである。光でこそないが、高尾の作品《Sails》は風を入力面であるキャンバスに受け、イメージレベルではペイントを、構造体レベルではさまざまな出会いと交流を出力として作り出し続ける。その意味において写真的であり、「写真性」を持った作品である。
2000年に入り、ロザリンド・クラウスは「ポストメディウム」という概念を提唱しはじめた。彼女は「メディウムの再発明」という論文の中で、
写真は、決して固有性に身を落とすことのない、芸術の本質を探求する主要な道具となったのであるⅰ
とし、写真というメディアは美的対象としてのアイデンティティを主張することなく、理論的対象となることで、芸術と合流を果たしたことを示した。このことはスマートフォンの普及によって芸術家だけでなく全ての人々を対象として拡張している。誰もが写真家となる時代とは、写真家が人間と同義語となることである。それはいいとか悪いとかではなく、写真家はいなくなることである。これも写真のひとつの未来なのだなということを考えさせられる。
創造の領域を拡張する壮大なフィクション


高橋順平《Where is ND》
最後に、高橋順平《Where is ND》について触れて本論を終わらせたい。高橋は第一回から作品を提示してきている。今回の作品《Where is ND》は床置きされた3面のマルチスクリーンへそれぞれプロジェクションされた3本の映像作品、作品全体の中心に向けて、天井から吊るされ、音と連動して点滅する電球、その下に置かれた丸いテーブルとそのテーブルを中心に各映像に対応するようにおかれたコンクリートによって作られたオブジェ3体とのよって構成されたインスタレーション作品である。
まず、はじめに本作《Where is ND》に触れる前に、昨年秋の修士1年生展の「HOP展」、さらには今年1月に行われた学部4回生の大上巧真との二人展「ウサギ・ハチドリ・ホムンクルス〜新しい地平の作り方〜」に軽く触れるところからはじめたい。
「HOP 展」において、高橋は巨大なビニールハウスとその中に入れた工事用のバルーンライト、敷き詰めた土とコンクリートのオブジェによって作った遺跡のようなもの。そして3つのモニタを使ってそれぞれに映し出した山の中に設置されたビニールハウスとその中の工事用ライトの定点観測の映像によって構成されたものであった。これは彼が自身の実家を中心とした3方向の山の中に建てたビニールハウスとライトの光によって、亡くなった祖母の魂を送る儀式のようなものとして行われた一連の出来事を記録、再構築したものとなっていた。煌々と光るライトの灯りは、たしかに田舎の山奥では非常に目立つ三角形の頂点となり、その魂は道を見失うことがないのかもしれないと作品を鑑賞して考えた。その考えはたちまちに、筆者の意識を地上絵やピラミッド、イスラム寺院の屋根の幾何学模様へと意識を向けさせた。今でこそ、飛行機が飛び、ドローンによる空撮が手軽だからこそそれらは見ることが出来るが、それらがつくられた当時は何に向けたものだったのだろうかということを考えてしまう。それらは、人が人智を超えた何かに向けてメッセージを投げかけるために創造した巨大なアーティファクツだともいえる。
高橋がアートとして、自身の作品の比較対象として考えるのは、美術館やギャラリーといった制度の中で収まるものではなく、地上絵のようなものである。
夏の「HOP展」をアップデートして、臨んだ大上巧真との二人展「ウサギ・ハチドリ・ホムンクルス〜新しい地平の作り方〜」は壮大な魔術的世界がギャラリー内に構築されるものであった。ギャルリ・オーブではビニールハウスと3つのモニタの関係がややわかりづらかったが、中心に小型化されたビニールハウスと工事用バルーンライト、3方向の壁には映像作品を映すモニタ、そして、この二人展のテーマとなっている「縄張り」という領域を示したような抽象的な写真にドローイングを施したプリント作品が壁に貼られていた。
見事だったのは大上の手で描いた呪術的なペイント作品とその世界観と見事に相互作用していた点。そして、展覧会場内におけるありとあらゆる全てのものを自分たちの創造物によって埋め尽くすことによって、外界と遮断した領域を展開したことである。大上の展示エリアに入ってすぐに数センチ床がベニヤ板によって持ち上げられていることで、鑑賞者は常にギシギシと音をたて、作品が揺れるという不安定な足元になっている。その床は高橋のシンボル的なビニールハウスまで続くが、ビニールハウスの周りには土が敷き詰められている。そこではギャラリーの床を踏むことさえ出来ない。天井こそギャラリーのものではあったが、高橋に至っては、工事用のバルーンライトが自身の作品を照らすため、ギャラリーの照明さえ使っていなかった。ギャラリー内に入ったはずが、ギャラリーの要素がそこに無いという特異な経験は鑑賞者の身体性にまで影響し、アタリマエを揺さぶられ、その経験の前後で世界の景色が変わってさえ見えるものであった。
これらの展示の一連の流れの先に本展における作品《Where is ND》は位置づけられる。
虫は正の走光性という「習性」によって、自身の飛行をコントロールしているとされる。その「習性」を人間に利用されていたのが、コンビニエンスストアの外などに設置されていた紫外線発生ランプによる電撃殺虫器であった。今回高橋が中央に天井から吊るした音に連動して点滅する電球とその音はこの電撃殺虫器を匂わすものである。
インターネットの発達によって、わたしたちは様々な問題に対する答えを瞬時に手に入れることが可能となった。2007年iPhoneの発売以降のスマートフォンの普及はそれに拍車をかけ、問題に対する答え、つまり答えを知るという目的に対して誰もが一直線に向かうようになっている。検索やAIチャットなどは誰かが作り出した答えの集積であるデータベースにアクセスをしているだけなのだが、その勢いに歯止めはかからず、もはや「目的」に向かうというのはわたしたち人間の「習性」とも言える。もし、「目的」や「答え」というものが、誰かもしくは巨大なシステムに設定された紫外線発生ランプであったとしたら、わたしたちはそれに向かう虫であり、その末路は激しい電撃である。三つの映像作品はコンクリートのオブジェを目指したものであったが、一人称視点が中心から外へ向けてのプロジェクションになっていることによって中心から外側へ向かう映像、つまり電球を中心としたテーブルと3つのオブジェから離れていこうとするもののように見える。
《Where is ND》の中で提示される3本の映像作品は、「HOP展」、「ウサギ・ハチドリ・ホムンクルス〜新しい地平の作り方〜」時に作成したコンクリートのオブジェを日中に車で限りなく遠い場所へ置きにいき、夜中にそれを徒歩で探しに行くということを記録した映像である。自らに難しく達成できない「目的」を設定し、誰かが設定したかもしれないこの目的に向かって飛んでしまうという「習性」の先にある死を逃れるシミュレーションを行うというのが高橋のこの作品の狙いであると考える。つまり「目的」に達せないということがこの「習性」に対する克服となり、この企みの成功とも言える。
頭に設置したGoProのようなアクションカメラによって映像は一人称のゲームのような視点で進む。暗闇の中、京都市外の街並みは徐々に道が細くなり、暗くなっていく。各映像は1時間25分、3時間19分、4時間14分と長く、映像全体を鑑賞者に見せることが目的とは思えない。実際に4時間14分のものに関してはコンクリートのオブジェを発見するところを筆者自身見ることが出来ていない。しかし、会場のテーブルのまわりにそれら3つのオブジェが並べられていることが、この失敗を目指した企みが失敗したことをほのめかす。
現代において、高度に情報化した社会の中、さらには結果を求められる資本主義の中では、失敗することのほうが実は成功するよりも難しいのだ。「道に迷う」というのは目的地があるからである。目的地のない移動は無意味ではなく、その移動そのものが意味を持つことである。世界のすべてを「0(問題)」と「1(答え)」とに還元しようとするテクノロジーに対し、その「0」と「1」の間に意味を作ることがわたしたちに残された価値生成の方法なのではないかというのが高橋の《Where is ND》の示そうとしたことではなかったのだろうかと考える。
最後に、これのどこが写真なのだろうかという問いに答えて本論を締めくくる。
美術評論家、清水穣は論文「不可視性としての写真」の中で、
「写真性」を持つものをすべて写真とみなすⅱ。
とした。彼は写真というものの領域を平面や印画紙といったものに限定をさせていない。さらに、清水は写真の衝撃を「視覚の構造的な他者」を発見したこととしており、写真に写るものは世界の表象ではなく、「世界を見ている眼」であると説明をする。つまり、写真を「見る」と言った時、それは決して見ることができない不可視の「見る」を見ているということとしている。そして、この不可視な「見る」はレフェランのなかに配分され内在されるものとした。その上で、清水は写真を
写真-写真性-レフェランという基本軸があり、写真とは表現するもの、写真性は表現されるもの、そしてレフェランは表現であるⅲ。
と整理する。言い換えれば、「写真性」とは「視覚構造」であり、表象を単なるイメージから視覚構造の衝突である「レフェラン」に変える「表現」の中に現れるということになる。わたしたちが「POST/PHOTOGRAPHY(ポスト・フォトグラフィ)」と呼ぶ新たな写真性をもった新種の写真表現は衝突の中から生まれるということになる。
高橋は《Where is ND》という作品展示の中、電球と音と自身の体験を並置することで、現代の人間のもつ「習性」と「失敗することが難しい現代」に対する高橋の持つ「視点」という不可視な視覚構造を作り出している。最終的にそれは、高橋自身の体験へと出力されているのだが、一方で、「HOP展」、「ウサギ・ハチドリ・ホムンクルス〜新しい地平の作り方〜」という展覧会の中では遺跡のようなものの中の一部でしかなかったコンクリートのオブジェに新たな意味として付加されているとも言える。
本展「写真は変成する 3 INTERPLAY on POST/PHOTOGRAPHY」は清水穣のいう「衝突の場」を、INTERPLAY(交流)という名の下、各々の表現内部、メディアの存在論的な段階、ポスト・メディウム的視点、展覧会のレベルと様々な地点において衝突を同時多発的に発生させ、鑑賞者に新たな視覚体験を提供した。
コロラド大学の解剖学者イヴァン・E・ワリンの「新しい種は共生によって生まれる」という主張を意味する「symbiotic evolution(共生進化)」という考え方はダーウィンの進化論の中にほとんど書かれなかった新種の出現について説明するあらたな概念として注目されている。新たな創造性もまた、生命体の創造性と同様に、何かと何かの衝突した部分で顕れる。「POST/PHOTOGRAPHY(ポスト・フォトグラフィ)」として未知なる写真表現は新種としてこの混沌の衝突、つまりこの交流の中から生まれてくるだろう。
「POST/PHOTOGRAPHY(ポスト・フォトグラフィ)」とは何なのだろうか?
今回「POST/PHOTOGRAPHY(ポスト・フォトグラフィ)」のアーティストとして提示された若きアーティストたちは日常的にスクリーンの向こう側のイメージを触り、コミュニケーションのツールとして交換・共有を繰り返してきた。彼ら彼女たち自身が「POST/PHOTOGRAPHY(ポスト・フォトグラフィ)」のアーティストという自覚があるかというと必ずしもそうではなく、彼ら彼女たちの作り出す表現は、今時点では「名付けえぬ」なにか、まさに新種のウイルスである。
イメージやオブジェクトの創造に、常に進化するテクノロジーと並走する「装置」の介入があることは、この領域において、先行者優位は働かないことを意味する。絵画や彫刻などと違ってこの領域における「変化」は、達人や年長者からではなく、常に新たな参入者が作り出す。そして、「写真性」によって「写真」でないように見えるものも「写真」となって写真というメディアの新たな側面をわたしたちに見せてくれる。たぶんここがもっとも「写真」というメディアのもつ魅力的な部分であり、写真ウイルスというものの「写真性」という魔力なのだろう。
この名前のない新種の表現の中に「写真性」を見出し、「POST/PHOTOGRAPHY(ポスト・フォトグラフィ)」という名前与えて、丁寧にそれを未来の「PHOTOGRAPHY」にしていくことが写真というメディアに関わるわたしたちの仕事なのだろうということを彼らの作品表現を通して考えさせられたことである。
(文:北桂樹、撮影:大澤一太・瀋 宇昕)
ⅰロザリンド・E・クラウス前掲論文(124)、p. 51。
ⅱ清水穣、「不可視性としての写真」、『デジタル写真論 イメージの本性』、東京大学出版会、2020年、p. 214
ⅲ清水穣、「不可視性としての写真」、『デジタル写真論 イメージの本性』、東京大学出版会、2020年、p. 221
京都芸術大学 Newsletter
京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。
-
京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts
所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス
連絡先: 075-791-9112
E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp



