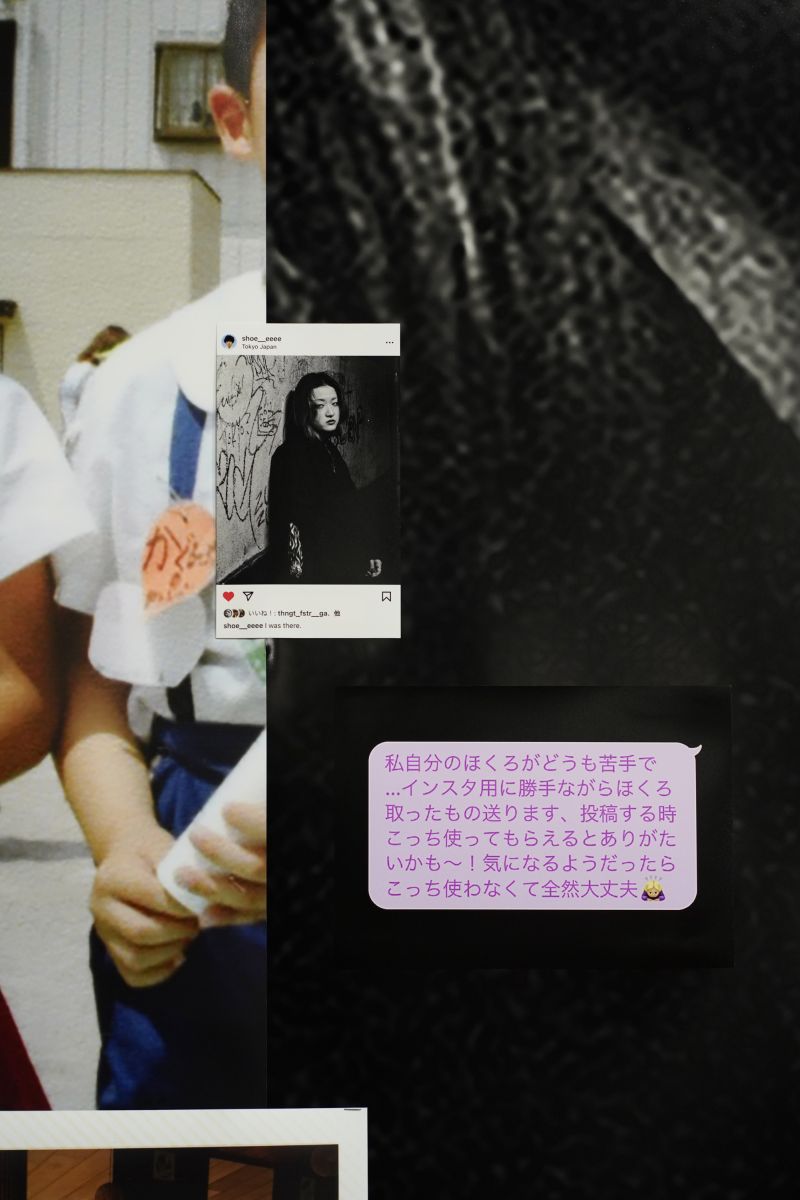インタープレイから生まれるもの ―「写真は変成する3 INTERPLAY on POST/PHOTOGRAPHY」京都芸術大学/大学院(写真・映像)+東京工芸大学 共同選抜展
- 京都芸術大学 広報課

文:藤本流位
1997年京都府生まれ、2019年に京都造形芸術大学(現:京都芸術大学)歴史遺産学科を卒業、同年に立命館大学大学院先端総合学術研究科に入学。「2000年代以降の現代美術における暴力の表象」をテーマとした学術研究に取り組んでいる。現在の主要な研究対象はスペイン出身のアーティストであるサンティアゴ・シエラ。
本レビューについて
本稿は、会期最終日である3月4日(土)に開催された講評会を踏まえながら、本展覧会に提出された作品に対する解釈を示すものである。その際には、それぞれの作品の間に見られる共通点・関連性などに目を向けることによって、展覧会のタイトルになっている「インタープレイ」という問題提起への応答を試みている。そのため、本稿は、本展覧会に対するレビューに重点が置かれた、後藤・多和田が主導してきたプログラムとしての「ポスト・フォトグラフィー」というアイデアそのものに対する解釈の色合いは薄いものになっていると言えるだろう。
2023年2月20(月)から3月4日(土)まで、京都芸術大学内のギャルリ・オーブにて展覧会「写真は変成する3 INTERPLAY on POST/PHOTOGRAPHY」が開催されていた。本学教員の後藤繁雄と多和田有希が主導してきた「POST/PHOTOGRAPHY」展は、今年で第三回目となり、今回は多和田と同様に美術工芸学科 写真・映像コースの教員である髙橋耕平、そして東京工芸大学芸術学部 写真学科の教員であり、後藤が主宰する「G/P gallery」でも展示経験のある川島崇志を迎えた4名の共同キュレーションというかたちで実施されている。そのため、出展作家は本学の写真・映像コースの学生、院生のほか、東京工芸大学の在学生・卒業生から選抜された合計15名のアーティストを交えたものになっている。
ギャルリ・オーブのなかに詰め込まれるようにして展示された作品群を見ると、それを他校交流展として単純に括るのではなく、タイトルにもある「インタープレイ」という言葉からもわかるように、外部と関わりながら、作品の意味を変成させていくといった目論見があるように思われる。
インタープレイ、すなわち「相互的なるもの」の要素は、アーティストの選出方法以外にも、アーティスト自らの作品生成の方法論、展示空間の構成など、実際に会場を訪れて、作品同士が錯綜する空間のなかに身を置くことによって気付かされるものもある。
そこで本稿では、この展覧会のなかで意図されている「インタープレイ」というテーマへの一つの応答を示すものとして、会期最終日である3月4日(土)に開催された講評会を踏まえて、いくつかの作品に対する解釈を提示していくことにする。当日のスケジュールは以下の通り。
第一部 13:00〜 北桂樹氏、藤本流位(本レビュー執筆者)による講評
第二部 14:30〜 キュレーター4名による講評
第三部 16:00〜 大岩雄典氏、布施琳太郎氏による講評
アイデンティティのゲーム
会場の中央付近で一際目立つ作品がある。高橋順平(たかはし・じゅんぺい)による《Where is ND》である。中央に置かれた丸型の机を囲むようにして配置された3つのスクリーンからは一人称視点で京都市の街を徘徊する様子が映し出されており、それに加えて、展示空間にはセメントと土を混ぜ合わせてつくられた3つのオブジェクトが置かれている。そして、作品上部にはノイズとともに激しく点滅する電球が吊られている。
この映像について、高橋は、それぞれのオブジェクトを京都市内、それも限りなく端側に設置し、翌日に設置したポイントを目指す様子を記録したものであると語る。このような行為は、他者からすれば無意味に見えるかもしれないが、自分から進んで「ゲーム」を設定し、それをクリアするという感覚は誰にとっても経験的に理解できるものだろう。
また、高橋は、これまでに自身が開催してきた展示においても、しばしばこのオブジェクトを使用し、展示の度にその役割が変わっているという。それはわたしたちが日常的に携帯しているデバイスと同様に、ある意味を入れるための容器のようなものだと言える。しかし、ビデオゲームのように仮想的に終始するものとは異なり、最長で4時間を超える徘徊の記録とオブジェクトは、高橋自身の身体的な苦痛を投影した証左になっている。
高橋の作品のとなり、壁面に展示されているのは、大矢彩加(おおや・あやか)の作品《ひと塊の執着》である。大矢はセルフポートレイトを主要な素材としながらも、その中心的なモチーフとして自らの鼻下にある「ほくろ」に焦点を当てている。
提出されたイメージは、幼少期に撮影された写真や、会話のメッセージの断片といった個人的な記録のほか、蓮の実、風に揺れる日本国旗、シミのついた地面など、スナップのようでもあり、画像検索で獲得したもののようにも見える出力物が錯綜しながら配置されている。
ほくろは、個性としても受容されるが、当人にとっての深刻なコンプレックスにもなりうるものである。しかし、この個性とコンプレックスの両義性は、常に表裏一体のものであり、他者に判断されるべきものではないにしろ、離れがたいイメージとして身体に定着している。一つのアイデンティティ・ポリティクスだと言ってもいい。
キャプションに目を向けると、それが大矢にとってコンプレックスであることを理解することができる。しかし、スマートフォンのカメラロールから切り出してきたかのようなイメージとの連関によって過剰に強調されたゾワゾワする感覚は、コンプレックスとしての側面だけを提示しようとするのではなく、そのゾワゾワとほくろを接続させることで、一つの快楽にしようとしているかのようでもある。
天使と瓦礫
個人に関連した行為や問題意識を素材とするのではなく、イメージの生成そのものへと焦点を当てようとする作品もある。高尾岳央(たかお・たけひろ)の《Sails》は、木組みで制作されたフレームに「船の帆」のように張られた支持体に対してエアブラシによるドローイングが描かれた作品である。フレームには車輪が付けられていて、展示空間のなかを自由に移動し、他の作品へ介入できるような仕掛けになっている。
高尾の作品は、一見するとドローイング的な要素が強いため、それが「写真展」に置かれているということに疑問を感じるかもしれない。しかし、キュレーターの川島は、高尾のエアブラシの手付きから、シャッターを切ることとの関連性を見出し、その刹那的な行為によって生成されるイメージを作品として成立させるという判断のなかにドローイングと写真との近似性があるのではないかと指摘する。
介入的に作品を挟み込むという行為は、この情報過多と言ってもいい空間を利用しながら、そのなかでどのようにしてイメージを経験させるのかということを指向しているように思われる。また、作品に描かれた「天使」のイメージからは、ヴァルター・ベンヤミンの指摘を想起することができる。ベンヤミンは、パウル・クレーの《新しい天使》(1920年)という作品について、進歩という名の嵐に力無く飲み込まれていく不運な存在がそこに描かれていると述べている。
高尾のように「描く」という行為によって成立する作品もあれば、その一方で「削る」という行為によって成立する作品もある。森凌我(もり・りょうが)の《バー・ティーンノットがあなたを引き止める》は、カーテンを使用し、会場の一区画を取り囲むようにして展開されたインスタレーション作品である。
カーテンの内側には、透明のアクリル板が組み込まれた木材のフレームが設置されており、それをキャンバスのようにして、森自らによってオリジナルの様子が認識できなくなるまで削り取られたイメージが貼り付けられている。これらを中心として構成された空間は、そのほかにも意図的にダメージを与えられた出力紙などが展開されている。
森はこのイメージの生成方法を「スクラッチ&ペースト」と呼ぶ。たとえば、ゲルハルト・リヒターはキャンバスの上にペインティングを施してから、その表面をスキージーで削るという方法によってイメージを生成しているが、森の作品を踏まえて言えば、それは「ペースト&スクラッチ」と呼ぶことができるだろう。しかし、「削る」という行為が手前にある森の手法は、デジタル上で処理したものをさらに別のレイヤーに貼り付けるという感覚、すなわち「コピー&ペースト」を前提として認めたものだと考えることができる。
これに関連して、先述したベンヤミンの「天使」の話には続きがある。ベンヤミンは、クレーの描いた天使は後ろを振り向き、自らが後にするにつれて積み上がっていく瓦礫を見つめるのだと解釈した。しかし、これに対してアーティストのヒト・シュタイエルは「デジタルの肉片」(2011年)という論考のなかで、現在ではこの「瓦礫」という概念に変化が訪れているのではないかと指摘する。つまり、情報の回収と復元を際限なく可能にするコピー&ペーストによって、瓦礫=破片は、ただ見つめるだけのものではなく、わたしたちがそこから何か別のものを生み出すための素材へと変化しているのだ。
些細な、けれどアクチュアルなもの
本展覧会に提出されているのは、加速するデジタル環境下での経験を踏まえた作品だけではない。大澤一太(おおさわ・いつひろ)の《絶え間なく行われる官能的な行為 / 唐突なピリオド》は、アーティスト自身の日常的な出来事から出発した作品である。
その作品は、自動車教習所で事故に巻き込まれた自らの経験をモチーフに、展示空間には3つのリアシートを配置し、それぞれに対応するように車のルームミラーがセットになっている。そこに座ると、シートに取り付けられたスピーカーから流れるノイズとともに、車を運転しているときの目線が部分的に再現されているということがわかる。目線を上げてみると、ミラーは、壁面に設置されたモニターに映し出された車後部の窓ガラスを捉えた映像を反射している。映像からは男性がタバコを吸っている様子を窓ガラス越しに伺うことができる。
大澤の作品について、講評会のなかで大岩氏は、自動車運転が身体的にリスキーなものであり、その際にドライバーが用いる多方向的な眼差しに言及しながら、それを「命懸けのキュビズム」という言葉によって説明した。この言葉からもわかるように、わたしたちは現在も、特定のメディア環境のなかでは、全身を使いながらイメージを受け取っている。
しかし、スマートフォンの普及がもたらすイメージ経験の一つの形式は、身体を伴うイメージの受容に対する意識を希薄化し、それはおそらく今後もテクノロジーの発展とともに加速していくことになるだろう。「メディア」という言葉はもともと「身体の拡張」として定義されているが、その意味で言えば、自動車とはわたしたちにとって最も身近なメディアの一つである。大澤の作品は、今日における「メディア」の経験が、事故や失敗、あるいはそれらを予期させる緊張感によって顕在化されるものになってしまったことを示唆している。
小林菜奈子(こばやし・ななこ)の《風が吹けば桶屋が儲かる》は、より微細な出来事に焦点が当てられた作品になっている。
展示空間を取り囲むようにして吊り下げられた薄い布には、じっくりと見つめなければ確認できない濃度でイメージが転写されており、その布は作品中央に配置された送風機から送られる風によって揺れ動くような仕掛けになっている。
講評会のなかで小林は、このイメージの生成方法について、家電量販店のエアコンなどに設置された風が出ていることを確認するための布から着想を得ていることを明らかにし、それと同様にカメラに布をつけて、ビル街を歩きながら、そこで吹きつける風に従ってファインダーを覗くことなくイメージを収集していったという。また、それを出力物するときには、収集したイメージのなかに関連性を見出し、さながらパズルのようにしてデータが作成されている。
ランダムなイメージの収集、個人の恣意的な関連付け、そこから派生するさらなるイメージの生成といったスキームは、今日におけるフェイクニュースのような、悪意に満ちたフィクションの生成に近似した方法論のように思われるかもしれない。
しかし、小林の作品は、そのような悪意を前提とするのではなく、「風」という目には見えないが、この身体に確かに吹き付ける感覚によって捉えられるイメージを素材としている。それでもなお、わたしたちは他者であるがゆえに小林の感覚を完全に把握することはできず、そこにあるイメージは送風機の人工的な風のなかで揺れ動き続けるのである。
都市が見ている
小林のように「都市」をテーマとした作品はこのほかにも見受けられるが、それらは、より高密度に発展した社会的な状況下でのイメージ経験を前提としている。
宮本十同(みやもと・じゅうどう)の《The twisted border》は、イメージが出力されたトレーシングペーパーを、3点の支柱によって支えるかたちで、捻りながら接合された「メビウスの輪」として提出された作品である。そのイメージは「皇居」がテーマとなっていて、宮本自身が「皇居ランナー」のようにして外周を歩きながら撮影したものが一つにつなぎ合わせられている。
東京は、ロラン・バルトが指摘するように、皇居という空虚な中心からなる都市である。象徴的な存在でありながら/あるがゆえに、皇居は、都市機能という側面から見ると、明らかに合理性を欠いており、その内実の肝心な部分も人目に触れないように構築されている。
この空虚な中心の外縁だけを撮影し、メビウスの輪として提出することにどのような意味があるのだろうか。このことに関連して、先述したヒト・シュタイエルの作品にも「メビウスの輪」がモチーフとなったものがある(ファッションブランドの「バレンシアガ」を対象とした作品《Mission Accomplished: BELANCIEGE》(2019年))。
シュタイエルによると、メビウスの輪によって囲い込まれたものは、その内部のエリアを私有地として指定するのではなく、その周囲のすべてを私有地として指定するのであるという。つまり、メビウスの輪とは、ドーナツ状のブラックホールのようになっていて、それは宮本の作品の場合だと、空虚でありながら、同時に象徴でもある皇居が、都市機能としての実質的役割を意に介さず、「象徴」という意味合いのなかにその周辺としての東京を回収しようとしているかのようである。そして、そのブラックホールは、周囲をただ回り続けるだけの皇居ランナーによって浮かび上げられているのである。
大橋真日菜(おおはし・まひな)の《人間という生き物は》は、より合理化された都市の機能にフォーカスした作品である。
二つの映像からなるインスタレーションは、積み上げられた資材の上に配置されたプロジェクターから壁面に投影されていて、右の映像からは、格子状に構成された青い鳥が規則正しく高速で回転しながら、そこから逸脱するようにして一匹が時折痙攣するように震えている様子を見ることができる。そして、左の映像からは、全体がモノクロームで構成された鴨川の様子を背景にマネキンが焚き火をしているように配置されている。このように記述すると、何か静謐なものとして感じられるかもしれないが、それは合成された「ネットミーム」のように人工的な冷たさを強調するようにして構成されていることがわかる。
目まぐるしく回転する鳥の映像は、鑑賞者に視覚的なストレスを与えるものであり、資材の上に配置された作品を見上げることから、鑑賞中は常に首にも負荷がかかるような仕掛けになっている。
目線より高い位置に展示されたストレスフルなイメージからは、都市に展開される広告との共通項を見出すことができるのではないだろうか。また、そこから想起されるのはミシェル・フーコーの「パノプティコン」の議論である。
姿の見えない位置からの眼差しを設定することで、最小数の監視で最大数の囚人を統治するパノプティコンという監獄のシステムは、現代では、監視カメラの普及に伴いながら、より高密度な形態となって社会全体へと広がっている。しかし、それは直接的な支配としての統治だけではなく、広告、すなわち他者に対する情報の発信という目的のなかでも利用されていると言えるだろう。
より合理的に、より多くの人々へと発信するために人々の目線を集めやすい位置に設置されたイメージは、それ自体がわたしたちへと向けられた眼差しのようでもある。わたしたちが広告を見ているのではない、広告がわたしたちを見ているのである。
さて、以上のように、本稿では「インタープレイ」というテーマにしたがって、部分的にではあるが、複数の作品を行き交うことで見出される要素を抽出し、提示してきた。作品同士を相互的に見ることによって、そこから関連付けられる意味、あるいは方法論・テーマの類似性は、本稿で示してきた部分以外からも見出すことができるだろう。
ここでは最後にキュレーションに対する見解を短く述べて、本稿を締めくくることにしよう。第三回目となる「POST/PHOTOGRAPHY」展であるが、今回はとりわけ自然物をモチーフにした作品、あるいは身体性への回帰といった作品が多く見受けられたこともあり、プログラム全体のテーマである「ポスト・フォトグラフィ」という観点から見れば、それらは少なからず反動的な主張のようにも感じられるように思われた。もちろん、それ自体が「ポスト・フォトグラフィ」の一側面であるということもできるだろうが、同時代的なテクノロジーのなかのハードコアな部分に身を浸すような作品がより多くあってもよかったのではないだろうかと考えてしまうことも確かである。
「インタープレイ」という方法論は、これまでのキュレーションにかけられていたバイアスを解きほぐすものとして意図されているようにも思えるが、そのような「インタープレイ」によって「ハードコア」が消失してしまうということはないはずである。
(文:藤本流位、撮影:大澤一太)

写真は変成する3 INTERPLAY on POST / PHOTOGRAPHY
京都芸術大学/大学院(写真・映像)+東京工芸大学 共同選抜展
| 会期 | 2023年2月20日(月)〜3月4日(土) ※会期中無休 |
|---|---|
| 時間 | 10:00 ~ 18:00 |
| 会場 | 京都芸術大学瓜生山キャンパス ギャルリ・オーブ |
| 出展者 | 大澤一太 Osawa Itsuhiro 大橋真日菜 Ohashi Mahina 大矢彩加 Ohya Ayaka 金田剛 Kaneda Tsuyoshi 菊池詩織 Kikuchi Shiori 小林菜奈子 Kobayashi Nanako シン・ウシン(瀋 宇昕) Shen Yuxin 高尾岳央 Takao Takehiro 高橋順平 Takahashi Junpei 道場美秋 Doba Minori 中川桃子 Nakagawa Momoco 成瀬凜 Naruse Rin 原田一樹 Harada Kazuki 宮本十同 Miyamoto Judo 森凌我 Mori Ryoga |
| キュレーション | 後藤繁雄 Goto Shigeo 多和田有希 Tawada Yuki 髙橋耕平 Takahashi Kohei 川島崇志 Kawashima Takashi |
京都芸術大学 Newsletter
京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。
-
京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts
所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス
連絡先: 075-791-9112
E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp