SPECIAL TOPIC2021.12.10
出口の見えない迷宮における思索と試作「in Cm | ゴースト、迷宮、そして多元宇宙」KUA ANNUAL 2022 プレビュー展
- 京都芸術大学 広報課
不確実な日々とズレから生成される展覧会
京都芸術大学では、2017年から学生選抜展 KUAD ANNUAL、2020年から KUA ANNUAL が開催されてきた。その特徴は、第一線で活躍するキュレーターを招聘して、全学生に対して募集・選抜を行い、制作指導を行いながらつくりあげていくこと。京都芸術大学のギャルリ・オーブで開催されるプレビュー展と、東京都美術館で開催される東京展の2回行われることだろう。キュレーターが出したテーマに対して、大学院を含めた全学生が応募し、そこから一緒に新作をつくりあげていくユニークな教育プログラムは、今まで多くのアーティストを輩出し、成果を上げてきた。
2017年度から2019年度までの3年間は、片岡真実(森美術館館長)がキュレーターを担当し、2020年度からは服部浩之(インディペンデント・キュレーター、秋田公立美術大学准教授、東京藝術大学大学院准教授、本学客員教授)が引き継いで実施されている。
服部は昨年、新型コロナウイルスによる100年ぶりのパンデミックの渦中にいる若いアーティストが置かれている状況自体をテーマにし、「現状に対して表現者として応答(Reaction /Response)してください」と呼びかけ募集を行った。彼らが「非常事態」の中で過ごした日常を見つめて制作した作品群は、「irregular reports:いびつな報告群と希望の兆し」と銘打たれて展覧会が開催された。
非常時の日常の中で、共に成長する展覧会 ― KUA ANNUAL 2021「irregular reports:いびつな報告群と希望の兆し」東京展
https://uryu-tsushin.kyoto-art.ac.jp/detail/795
服部がキュレーターとなって2年目となる今年は、「C|接触と選択」をテーマに募集が行われた。コロナ禍も2年目となり、何度も何度も感染拡大と収束を繰り返す中で、モノや人への「接触」に抵抗を覚え、行動を慎重に「選択」するように変化しているのではないか、という問いかけを行ったのだ。服部の投げかけられた問いに、合計87組106名から応募があり、そこから書類審査とプレゼンテーション審査を経て、15組18名の作家が選ばれた。また、今年も昨年から取り入れられたアシスタント・キュレーターが5名選ばれ、合わせて15組の作家を担当し、『キュレーター・ジャーナル』の発行など独自の活動を行った。
服部は、作家の様々なプランを見たり、制作を指導する中で、出口の見えない状況を感受し、世界が迷宮に入り込んだような、不安や不穏さが漂う表現が提示されていることに気付く。そこで「C」という明るい響きを連想するメジャーコードの記号ではなく、第3音が半音下がり、憂いを感じる響きを連想するマイナーコードの「Cm」の方がふさわしいように感じるようになる。また、ミニマル・ミュージックの代表曲としても知られるテリー・ライリーの《In C》(1964)の、ハ長調で短い旋法の反復でありながら、迷宮のような複雑さと多様さを形成する世界観に共通性を見出した。それらを合わせて展覧会タイトルを「in Cm」と命名し、さらに作家の表現から「ゴースト、迷宮、多元宇宙」というキーワードを抽出し副題に付けた。
2021年12月3日(金)の会期初日に行われた公開講評会には、浅田彰(ICA Kyoto所長、大学院芸術研究科教授)、竹内万理子(美術工芸学科学科長)、国枝かつら(京都市京セラ美術館アソシエイト・キュレーター)が招聘され、出品作家のプレゼンテーションと講評が行われた。最初に、浅田所長は、本展のテーマになっているタイトルについて、「C」が「Cm」になったところで、音楽的に言えば、7音階による調性音楽の要素に過ぎず「安定」していることを指摘した。確かに、シェーンベルク以降の12音技法や無調音楽によって不協和音が頻出したり、ジョン・ケージ以降の環境音やノイズと思われる音を取り込んだ現代音楽史の中で、20世紀半ばに出てきたミニマル・ミュージックは、民族音楽などの影響を受けながら、調性音楽を部分的に復活させている側面がある。
ただし、服部の意図は、作家の提案がどんどん変化していく中で、それに応答していくには少しずつずらしていかなければならかったこともあるという。そして、明確なテーマを打ち出すのではなく、混沌とした状況をそのまま提示する、という意味も「m」に込めた。その点では、同じくミニマル・ミュージックの先駆者であるスティーヴ・ライヒの《イッツ・ゴナ・レイン》(1965)の方がイメージに近いかもしれない。いずれにせよ、服部が冠した「in Cm」はメタファーに過ぎないかもしれないが、短調やマイナーコードの持つ「憂いの響き」が現在の世界を支配し、感染拡大と収束が反復する中で、展開が読めない不確実性や迷宮性を帯びていることをよく表している。そして、それが「調性」の範囲で展開されているとするならば、PC(ポリティカル・コレクトネス)が全面化し、過度に道徳化している社会や現代アートの状況を表しているといってもいいかもしれない。
それでは展覧会場で展開されている「in Cm」の不穏な迷宮世界を、キーワードを頼りに見ていきたい。
心と形の「迷宮」
服部が副題に付けた「ゴースト、迷宮、多元宇宙」というキーワードは、それぞれに重なって含まれているので、完全に切り分けられるものではないが、導入のために一つのメタファーとしてまとめていきたい。まず「迷宮」では、偶然ながら昨年選抜された作家を分類した。
ギャルリ・オーブ入口の壁面には、高尾岳央(美術工芸学科油画コース)が6枚の巨大な絵画を密接させて展示した。昨年度の KUA ANNUAL 2021 にも選抜された高尾は、グラフィティに影響を受けながら新しい絵画の可能性を探求している。今年は、車窓からの風景をテーマに、グラフィティのイメージを更新した。
グラフィティは通常、特定の場所に描かれており、その場所に向けたメッセージであることも多い。つまり、場所と切っては切れない関係にある。高尾は車窓の中から見る文字やキャラクターは場所との関係から切り離され、支持体を失って宙に浮いた存在になって印象に残ることを見出す。例えば、モネやピサロなどの印象派が、鉄道の風景を描き始めたことは知られているが、セザンヌの立体的な描写も、鉄道の車窓から遠景と近景が異なって見える効果が基になっていると秋丸知貴(美術史家)は指摘している。エアブラシによって描かれた線は、ある種の迷宮のような表象をしている。
高尾は21世紀において、車窓から見える文字やキャラクターを描くことで、風景画を更新しているといえるかもしれない。講評陣から言語化の未熟さと、作品ごとの質の差が指摘されたが、車窓の視点の発見により、グラフィティの表現との差異を発見したのは大きな進歩だろう。
同じく昨年度も選抜され、1ミリずつズレていく階段の作品を発表した戸田樹(美術工芸学科総合造形コース)は、今回は迷宮をモチーフに巨大なスピーカーを制作した。
しかし、それは一見すると巨大な壁面になっており、裏と表を一度に見ることができない。裏側は木製のクレタ型迷宮が象られており、分岐のない一本道が曲がりくねっている。迷宮はギリシア神話ではミノタウロスが閉じ込められた場所とされるが、ミノタウロスは牛頭人身の怪物で、ピカソが自身を投影したことでも知られる。そのような、野蛮な男性性や父性が閉じ込められているという隠喩になっている。
表側には中央にスピーカーが埋め込まれ、音声が流れている。戸田は、祖母からもらったカセットデッキに幼少期から様々な音を録音しており、最近、再発見し、聞き直していたという。そこに、幼い戸田が遊んでいる音の背景で、父の怒声などが入っており、父との相克が刻印されていることに気付く。その記憶の中に潜む父に対する恐怖と嫌悪、そして父と同じ性質が自身の心の中にあることを自覚し、それを表現すると同時に、迷宮に閉じ込めることを試みている。迷宮は、低音を増幅するバックロードホーンの隠喩にもなっているが、塞がれていないため機能をしていない。
講評陣からは、迷宮が俯瞰的になっており、2次元的、イラストレーション的になっているなどの指摘がなされた。音量やスピーカーの形も含めて検討の余地はあるだろう。あるいは、ヴィト・アコンチの《シードベッド》(1972)のように、壁面とスピーカーを抑圧と無意識の構図として捉えて展開してもよかったかもしれない。例えば、野獣のような声が内部で鳴り響いて、壁面の迷宮の中をめぐって消えていく仕組みになっていればさらに説得力があっただろう。
長田綾美(大学院美術工芸領域)は昨年度、辞書を細く切り抜いて、巨大な織物を制作した。それ以前は、ブルーシートを丹念に編み込んでいき、工事や被災を強く連想させる素材のイメージを変容させる作品を制作しており、日用品を主な素材としていた。今回は、自然物を扱うことを考え、バラス(砕石)を利用した。
バラスは元々バラスト(ballast)であり、船に積む重しという意味合いであった。気球の重しや鉄道の線路にも使われ、安定のために使われている。それらを巨大な不織布に一つひとつくるんでいき、蛍光色の水糸で巻いている。不織布の用途は、コロナ禍で著名になったマスクを連想するが、それだけではない。ビニールハウスシートのように農業や園芸資材、土木、製造業など多くの用途で使われているが、極めて破れやすい。その不安定な素材と安定のための砕かれた石という対比的な要素が同居しており、見るものを不安にさせる。約5か月かけて編み込まれ、奇跡的に破れていない不織布は、まるで今にも壊れそうな我々の世界や生活のよう思えてくる。また、巻かれた水糸は1本をつないだものであり、まさに1本道の迷宮になっているといえよう。講評陣からは、繊細ですぐ破れてしまうかもしれないが、もう少し重力を感じる展示になっても良かったのではないかとの指摘がなされた。
昨年度は、自身のエージェントとして竹と紙で人形をつくった柯琳琳(美術工芸学科日本画コース)は、自分の身体の動きをテーマに「ダンス」ゲームを制作した。柯は、近年増えているADHDのような「不注意」と「多動・衝動性」の傾向を自身にも感じて生きてきた。そのようなタイプの人々は、身体拘束や近代化の過程でつくられた規範的な動きに対して、強い違和感を持つ。柯は、ダンスゲームがある種の動きのパターンを積極的に合わすことで得点が得られるということに、社会が強要する身体的な規範と共通性を見出し、それを逆転させて、自身の奇妙な身体的な癖を模倣することで得点が得られるゲームをつくり出した。
スクリーンには、インストラクターとなった柯が、自身の動きを「ダンス」として披露し、それを床に設置された八方の矢印を踏んで観客が真似をする、インタラクティブなゲームを模したメディアアートになっている。また時折、スクリーンには、柯の顔の表情も現れる。竹内教授からは、スクリーンにそれらの2つの映像が重なるため、観客が見えづらくゲームがしにくくなっている、という指摘があった。しかし、近代以降の社会規範がつくった動きの強要を逆手にとったユニークな発想であり、ゲームの精度が上がると柯の動作に伴う生きづらさが観客に憑依することになり、多様性を体感する意味でも可能性があると思える。
多様な人々が同居する「多元宇宙」
「多元宇宙」では、広義の意味で他者を意識した作家の作品を挙げていきたい。シャンツァー・アルマ(大学院博士課程)は、いわゆる「引きこもり」の人々の肖像を8×10インチ(エイトバイテン)の大型カメラを使って定着させた。
8×10インチとは約203.2mm×254mmのフィルムサイズを持つ現行では最大のカメラだ。これ以上細密に撮影できるアナログカメラはない。それをフィルム以前の古典技法、湿板写真によって、ガラス板に直接的に印画している。しかし、引きこもりの人々の肖像は、直接的ではなく、プロジェクターで映し出されたもので、シルエットになっているためディテイルはわからない。印画されたガラス版は、家の廃材の板を再利用した箱を閉じるように組み込まれ、「カメラ・オブスキュラ」(暗い部屋)の隠喩になっている。その小さな「暗い部屋」が、スチール製の高さの違う台座に置かれ、正面を変えて設置されている。
引きこもりは、英語では Social withdrawal と訳されるが、Hikikomori として近年、世界でも知られている。しかし、日本に加えて、韓国、中国、イタリア、フランスなど家族主義の国々で見られる。アメリカやイギリスなど個人主義の国では外に出されるためホームレスとなる傾向があるからだ。アルマは、自身も病気を抱えて家から出られない経験があり、日本の引きこもりに関心を持った。それで引きこもりの家族会などに参加するなどして、それぞれの事情をリサーチし、SNSなどで当事者にコンタクトをとるようになる。そして、彼らの自身の肖像画像を送ってもらい、それを基に本作を完成させた。
湿板写真は、1851年イギリスのフレデリック・スコット・アーチャーが発明し、ダゲールが1839年に発明したダゲレオタイプ、トルボットが1841年に発明したカロタイプを駆逐し、主流となった。幕末から明治初期にかけて日本で撮影された写真は、湿板写真だ。湿板は、ガラス板にコロジオン溶液とヨウ化銀の混合液を塗布して膜をつくった上で、硝酸銀の溶液に浸してヨウ硝化銀の感光膜を得たものだ。「湿板」というように湿ったままでカメラに装着し、撮影してすぐに現像しないといけない。そのため撮影の場所は大学か、自宅になるが、部屋の設えには被写体の個性を連想させるものを置いている。
被写体は、最初から引きこもりだったわけではなく、学校や社会に出て、環境によって精神あるいは身体に疾病を抱えたものが多い。アルマはそこには偏見があると述べる。心身に不調をきたしたのも、閉じ込もることができる環境も社会的なものだといえる。アルマは「そこには安心もある」とポジティブな側面も指摘する。そのような社会の無意識ともいえる人々の存在を、物質性の希薄なデジタル画像から、湿板写真によって物質化し、可視化したといえるだろう。講評陣の評価も高かったが、箱の中の処理などに少し課題が残った。その点は、東京展で改善されるだろう。
いっぽう向珮瑜(大学院美術工芸領域)は、LGBTQ+の東アジアの女性に対して膨大なインタビューとリサーチを重ねてきた。彼女たちとの対話は、中国語と日本語に翻訳され、レシートプリンターによってロール状の感熱紙に印字されていく。切れ目のない感熱紙は天井から吊り下げられており、ぎりぎり判読が可能な小さな文字が印刷されている。また、壁面にはLGBTQ+を想起させる虹色のネオン管などが展示されている。レシートに使われる感熱紙に印字されている文字は、読もうと努力しないと読めない。すなわち、LGBTQ+の東アジアの女性の声はそれだけ小さいことの隠喩になっている。また、感熱紙は熱や光、油などに接触したり、時間の経過によって容易に消えていく。すなわち、彼女たちの声も小さく、そして消えやすいのだ。しかし、その文字は大量にあり、多くの存在がいることを表している。
ネオン管は、具体的なものを表す象徴的なものではなく、向のメモからつくられたものだという。しかし、虹などの色彩や形などにLGBTQ+の表象が読み取れる。竹内教授からは、レシートを連想させる小さく消えやすい媒体を使ったことはよいのではないかと評価を受けた。浅田所長は、フェリックス・ゴンザレス=トレスの《Untitled (Perfect Lovers)》(1987〜90)の例を挙げ、ネオン管のオブジェについては検討の余地があるのではないかと指摘した。
あるいは吉田コム(美術工芸学科総合造形コース)は、手紙を使ったメールアートと、GPSを付けた石、会場に設置された単眼望遠鏡によって、他者の存在の意識化を行っている。吉田は新興住宅地で育ち、自身が計画の中の一部になっているのではないかという違和感を覚えるようになる。その中で、他者の存在を認識しつつ、距離を維持したままで、上下や利害関係を持たないコミュニケーションの在り方を模索してきた。
本作では、海外在住者からオークションで取得した、何が撮影されたかわからないファウンド・フォトを50枚複製し、それを見たら自分に返送してもらえるよう手紙を入れて50軒に投函していった。会場には複製された50枚の写真の横に、返送されてきた4枚の手紙がテーブルに並べられていた。また壁面には、どのような依頼を書いたのか少し内容がうかがえる手紙セットの拡大写真が展示されている。GPSが付けられた石は、プロジェクターで投影されたGoogleMap上にポインティングされている。また、吊り下げられた単眼望遠鏡をのぞくと、オーブの屋上付近の窓に「When people passed by each other HERE(ここで人と人がすれ違ったとき…)」とポストイットが貼っているのが見える。
手紙は返信されてきても封を開けず、返信してきたという事実のみが提示されている。どの試みも、気付きや認識するレベル以上進まないように設定されており、リレーショナル・アートやソーシャリー・エンゲイジド・アートとは違った、深く関係を結ぶことを拒否した試みになっている。積極的な不干渉主義といってもいいかもしれない。講評陣からは、やりたいことが明確であるが、展示方法については改善する余地があると指摘された。
それに対して、「東九条耕す計画ただいも」(情報デザイン学科1名・美術工芸学科3名)は、京都市南区東九条周辺の使われていない土地を耕すアーティスト・コレクティブである。
2020年5月から活動を開始し、「普通(ただ)のいも」、「ただいま」、「無料(タダ)」などの意味を込めたコレクティブ名を冠した。この地域は、社会的マイノリティが住んでいた経緯がある。その過程でつくられた公共施設に属する使われてない土地を「耕す」ことを試みた。つまり、そこには更地ではあれども、様々な都市の歴史があり、現時点でパワーバランスが均衡しているがゆえに使える状態にある。「東九条耕す計画ただいも」は、その歴史の隙間に介入し、畑にしてゴーヤやプッコチュ、リーフレタス、サツマイモなど、様々な種を植え、食物を耕していった。同時に、地域住民と交流することで関係を耕していっている。それらの過程を絵日記にして、会場の壁面に展示した。また、天井からはサツマイモの根に見立てた紐をぶら下げ、来場者に質問を芋の形の紙に書いて、吊り下げてもらい、言葉の芋の繁殖を試みた。
竹内教授からはこのプロジェクトを展示する方法についてはもう少し考える必要があるとの指摘があった。また、浅田所長からは予定調和に陥らず、行政の意向を反転することの可能性も示唆された。例えば、ミュンスター彫刻プロジェクトでフィッシュリ&ヴァイスが作った菜園(ガーデン)のように、気付くか気付かないかギリギリのレベルで作品にするという可能性もあるかもしれない。そうではなく、社会包摂型のアプローチとして続けることも可能であろう。絵日記のようなアプローチも学芸会的ではあるが、それが複雑な場所に介入する際の、警戒心を取り除くための慎重な手続きとして考えることもできるかもしれない。
自身の記憶や身体に潜む「ゴースト」
「ゴースト」は、自身の中に潜むものを映像的・平面的に表現した作家の作品を挙げていきたい。岩橋優花(大学院美術工芸領域)は、モノクロフィルムによるストレート写真も撮影しているが、本作では、過去に撮影した写真や遠方に住む友人とZoomでつないだ映像を切り取ったポートレートをプロジェクターで不織布に投影し、モノクロのフィルムカメラで撮影している。
不織布の前には、花や木の根が置かれており、より複雑で錯綜した状況が写真に定着されている。プロジェクターで投影された暗い環境で撮影しているため、必ず白い光源の跡が入り込んでおり、木の根がニューロンに見えることからも、発火によってシナプスが結合し、記憶が蘇る脳内の状況を再現しているように見える。暗い洞窟のような脳の中を、イメージを重ねることで、探訪するようにも見え、観客は岩橋の脳を垣間見るような奇妙な気持ちを覚えるだろう。浅田所長は「心霊写真のようだ」と指摘したが、まさに岩橋は「脳の中の幽霊」(ラマチャンドラン)を写しているといえるだろう。
いっぽう太田恵以(大学院グローバル・ゼミ)は、心身の中に潜む2つの人格をテーマにした。太田は、日本生まれであるが、27年間アメリカで過ごし、16年間ニューヨークでダンサーとして活動してきた。つまり、1つの心身の中で、異文化の言語と身体を行き来し、分裂と翻訳を繰り返してきた。今回は、日本人としての人格とアメリカ人としての人格が対話する情景を映像に収め、4枚の透過するスクリーンを重ねて投影した。4枚のスクリーンはプロジェクターの手前から徐々に大きくなるが、その逆に映像は透過を繰り返してぼやけていく。それは、二国間で揺らぐアイデンティティや翻訳の不可能性の隠喩となっている。
プロジェクションによる表現は、19世紀にマジックランタン(幻燈機)による幽霊ショー「ファンタスマゴリー」によって大衆化された。そこでは、半透明の幕が使われ、幻燈機を動かすことで、幽霊の出現が演出された。今回、キャスターがついた移動可能なスクリーンを制作しており、自身のダンスと合わせて、パフォーマンスとして展開することも可能だろう。浅田所長や国枝氏ら講評陣からも、舞台美術の可能性があることが示唆された。
高橋順平(美術工芸学科油画コース)は、自身の皮膚をテーマにしたインスタ―レーションを展開した。まず、自身の皮膚を接写し、プリントアウトして、地中に埋める。3週間、毎日水やりをしてプリントの腐敗を進行させ、再び掘り起こす。プリントは地中で腐食し、分解され、崩れた紙と皮膚の画像は混じり合い、一つの「老化した皮膚」となっている。それらを再撮影して、巨大な布にプリントして、会場に吊られたり、巻いて展示されている。また、それらは扇風機が当てられており、生きているかのように揺れている。地中から掘り起こされた皮膚は、ゴーストというよりもゾンビに近いかもしれない。
講評陣からは、インスタレーションとして高評価を受けたが、2本足がある人体モデルに見えることについては、検討の余地があると指摘を受けた。
大澤巴瑠(大学院美術工芸領域)は、10点の猫の絵画を展示した。しかし、これらの絵は、一つの猫のドローイングが基になっている。それを少しずつ動かしながら、何百枚もコピー機で複写し、様々な歪みやズレが生じたコピーから10点を選んでそれを原画とした。絵画にするにあたり、麻布をはって白いアクリルを塗り、墨で描いているため、その過程では「模写」となっている。自身の身体的な動きで描いたドローイングを、機械でズレを増幅させ、それらをまた別のメディウムで写し取る工程を経ることで、原画と複写の概念にゆさぶりをかけている。国枝氏からは、すべての絵が猫と把握できるため、原画が想像できてしまうので、猫と認知できない画像を多く使った方が良かったのではないかとアドバイスがあった。
松田ハル(大学院グローバル・ゼミ)は、大学時代に版画を修め、様々な技法に習熟する中で、版画に潜む根本的な欲望を考え、空間の拡張や創造ということにいきつく。今回松田が試みたのは、版を重ねる度にイメージが少しずつ壊れる版画の性質を活かして、仮想空間と現実空間を合わせ鏡のようにした重層的な版画空間を創造することだ。具体的には、現実空間と仮想空間の中で、複写を繰り返しながら欠落したり変容していくイメージをつくり、両方を往還して体験するインスタレーションとして再構成した。例えば、自身の顔や観葉植物を3DスキャニングによってVRデータ化し、それらを基にVR上で加工して、シルクスクリーンや木箱にドローイングを行っている。元になった観葉植物が人工芝の上に置かれていたり、床から平行に突き出るように設置されており、仮想空間内のイメージが投影されている。目視で見ると奇妙なインスタレーションは、仮想空間の反映であり、何らかのイメージが欠落している。
VRゴーグルをかぶると、空間が反転されており、天井と床には水面になっている。そこには観葉植物など、現実空間のオブジェが3D化されたものがあり、仮想空間上を歩くと同じ位置に行けばぶつかってしまう。つまり、現実と仮想が同一の3次元上でつながる固まりがあり、拡大された空間ではなく重層化されていることに気付かされる。ただし、どちらかに行けば、何かが欠けているし、どちらにも欠けているものもある。現実空間のインスタレーションには、松田の口や観葉植物のデータと合体した身体などがペイティングや版画などに刻印されており、不在の松田の存在がさらに見えない版となっているように思える。
講評陣からは、全体的な構成や個々の作品の完成度が高いと評価され、特に浅田教授は歪んだ口のペインティングは、フランシス・ベーコンを想起させるとし、また、ペインティングに見えるシルクスクリーンに関しても評価した。ただし、VRゴーグルをつけない観客の想定と、重層的な仮想空間の中で、音響が水の音しかないことの違和感が、国枝氏から指摘された。その点については改善の余地があるだろう。松田の作品は、新型コロナウイルスにみられるように、自己複製と変異こそが、創造や進化の仕組みであることを示唆するものにもなっているといえる。
柴田眞緒(美術工芸学科油画コース)は、自身の「要らないけど、捨てられない」物体を、樹脂によって固めて床に並べて展示した。そこには中学時代の旅行用ネームタグやポラロイド写真、絵の具のチューブなど、他者にとってはゴミに見えるが、柴田にとっては重要な記憶が残っているものが封じられている。しかし、柴田にとっても確かに飾って残すほどのものでもないだろう。そのように、捨てるには躊躇するものは生活の中に多数あり、形が不定形のため、室内の整理の邪魔になっているものは誰にでもあるだろう。かといってすべてデジタル化することも難しい。そのような物質に埋め込まれた外在化した記憶を視覚化したといってよい。
大野裕和(美術工芸学科総合造形コース)は、もう一つの展覧会として、ギャルリ・オーブをVR上でつくり、出品作品を展示した映像作品を上映した。コロナ禍になって、オンラインで鑑賞するための取り組みが行われたり、3Dスキャニング撮影で、展覧会場を記録することが行われるようになったが、現実の空間は理想的な鑑賞空間だとは限らないし、完成された作品が出品されているとも限らない。多くの場合、金銭的、物理的、技術的制約の中で、自身のイメージよりも劣ったものを妥協して展示しているということがほとんどである。今回の映像は、出品者の作品がぎりぎりまで調整が行われていたため、一部しか反映されていなかったが、将来的には理想的な展覧会や、実現しなかった「アンビルド」な展覧会の可能性を示唆している。
すでにコロナ禍も2020年、2021年と丸2年続き、新たな変異株の登場により、来年以降の楽観的な予測は裏切られつつある。特に今年は、東京オリンピックと過去最大の感染拡大が重なり、多くの人々が予定も大きく変更せざるを得なかった。アシスタント・キュレーターが展示したタイムラインを見れば、それらの状況が、生々しく思いだされる。ワクチンの普及だけでは、容易に収まらない状況の中で、これから世界に出るアーティストたちがどのような表現をしていくのか。出品作家の表現はまさに、マドルスルー(muddle through)と言われる出口のない泥の中を進んでいくように思える。目標や出口が見えない中で進むこととの重要さとしてベンチャー企業で使われる言葉だが、その手探りから鉱脈を見つけると言われている。それはコロナ禍における若いアーティストにも当てはまるように思える。
服部が、「自身の活動や表現を他者に対して『ひらく』柔らかさを持っているか」ということ一つの選考基準としたと述べるように、この状況の中で生き抜くには、頑固さではなく、柔らかさであるように思える。出口のない迷宮の脇道で拾ったもの(経験)こそ実は次の道を切り拓く鍵ではないか。本展では、それぞれが次の道に進むための思索や試作が見られるだろう。それは観客にとっても重要な問いになっているに違いない。
(文:三木学、作品撮影:顧剣亨、講評会撮影:岡はるか、広報課)

KUA ANNUAL 2022「in Cm | ゴースト、迷宮、そして多元宇宙」プレビュー展
| 会期 | 2021年12月3日(金)~19日(日) |
|---|---|
| 時間 | 10:00~18:00 |
| 場所 | 京都芸術大学 ギャルリ・オーブ |
| 入場 | 学内関係者のみ。一般の方は土日のみ入場可 ※要予約 |
京都芸術大学 Newsletter
京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。
-
京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts
所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス
連絡先: 075-791-9112
E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp




.jpg)







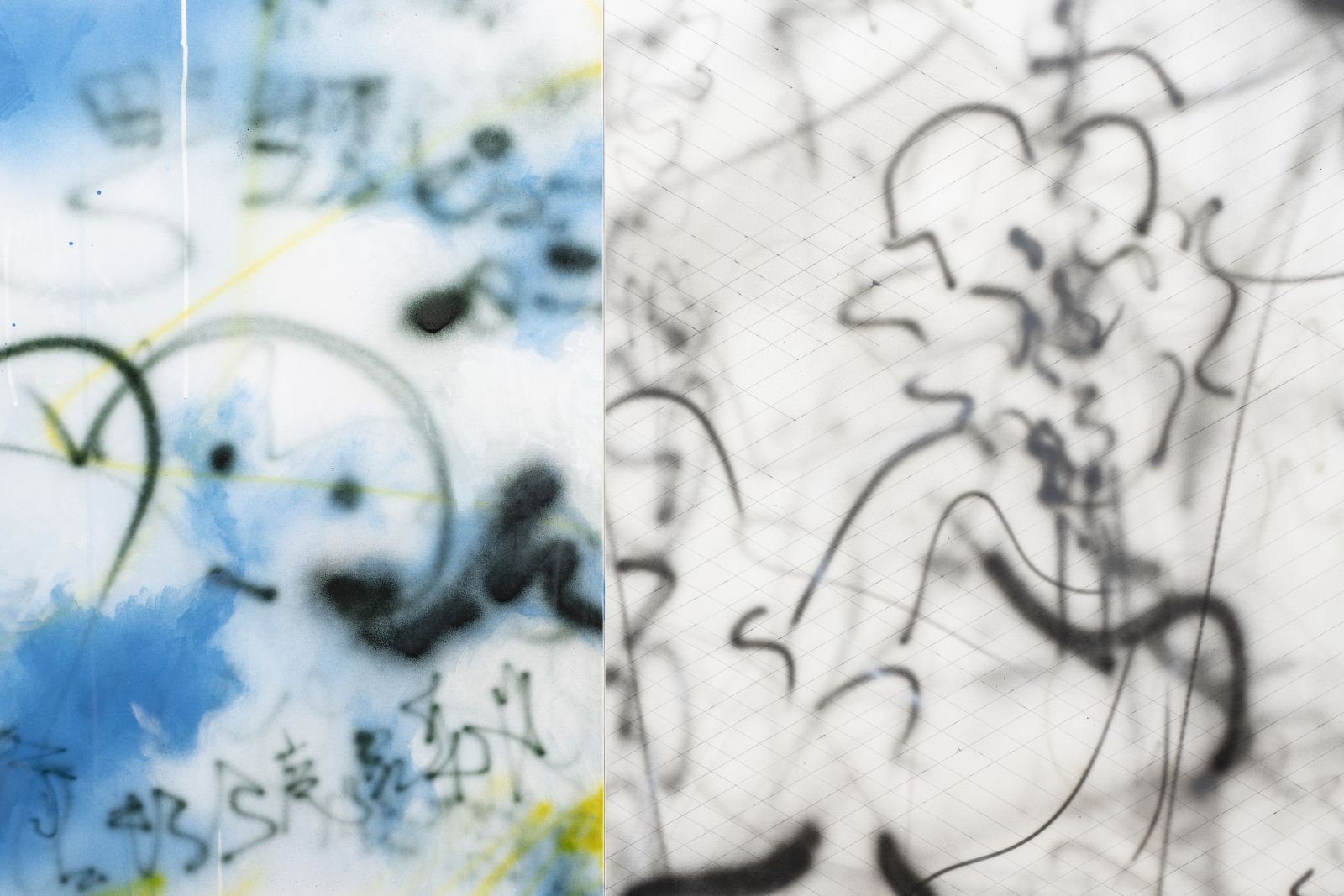
.jpg)


.jpg)


































.JPG)






