SPECIAL TOPIC2022.10.12
ICA京都が大型イベントを初開催! - 京都、チェンマイ、ジョグジャカルタの繋がりから見えてくる現代アートの「キャピタル」とは?
- 京都芸術大学 広報課
2022年8月11日(木)、京都芸術センターでICA京都の創設記念国際シンポジウム「現代アート・キャピタルの潜在力──京都、チェンマイ、ジョグジャカルタを繋ぐ共同体」が開かれました。
ICA京都は、京都芸術大学の附置機関として2020年4月に創設されたものの、新型コロナウイルスの感染拡大による2年弱の低空飛行を経て、このたび初の大型イベントの開催へと至りました。
シンポジウムの冒頭では、所長の浅田彰(批評家、京都芸術⼤学教授)より、ICA京都の特徴について以下の説明が行われました。そもそもICA(Institute of Contemporary Arts)とは、日本語で「現代芸術研究所」を意味する言葉。世界的には、1946年に創設されたICAロンドンがよく知られています。
常設のギャラリーやシアターをもたないICA京都に期待されているのは、シンポジウムやトークセッションの開催、アーティスト・イン・レジデンス支援など、アートにまつわる人的交流のハブとしての機能。本シンポジウムの会場になった京都芸術センターのように、京都にはすでに多くの展示施設、美術大学、そしてアーティスト・スタジオなどが存在しています。
ICA京都はそうした街の特性に寄り添いながら、既存インフラとのコラボレーションを前提としてスタートすることになりました。

ICA京都 創設記念 国際シンポジウム
現代アート・キャピタルの潜在力-京都、チェンマイ、ジョグジャカルタを繋ぐ共同体
■セッション1「アジアにおける現代アート・キャピタル」
チェンマイ、ジョグジャカルタを拠点としてグローバルに活躍するキュレーターやアーティストによるプレゼンテーションとパネルトーク
・クリッティヤー・カーウィーウォン(キュレーター/ジム・トンプソン・アートセンター芸術監督)
・栗林隆(アーティスト)
・小崎哲哉(ジャーナリスト/アートプロデューサー/ICA京都『REALKYOTO FORUM』編集長)
・ナウィン・ラワンチャイクン(アーティスト)
・アリア・スワスティカ(キュレーター/ジョグジャ・ビエンナーレ ディレクター)
*モデレーター:片岡真実(森美術館館長/ICA京都 顧問)
■セッション2「現代アート・キャピタルの潜在力」
アートを取り巻く環境の変化、そして京都が担うべき現代アート・キャピタルの可能性を探るクロスディスカッション
・青木淳(建築家/京都市京セラ美術館館長)
・サスキア・ボス(美術史家/キュレーター/批評家)
・クリッティヤー・カーウィーウォン(キュレーター/ジム・トンプソン・アートセンター芸術監督)
・建畠晢(美術評論家/詩人/京都芸術センター館長)
*モデレーター:浅田彰(批評家/ICA京都 所長)
京都、チェンマイ、ジョグジャカルタを繋げる視点
本シンポジウムのために、国内からの登壇者に加えて、国外からはタイのチェンマイ、インドネシアのジョグジャカルタからスピーカーが招聘されました。
ICA京都の顧問を務める⽚岡真実(キュレーター/森美術館館⻑、京都芸術⼤学客員教授)は、キュレーターとして世界各国を訪れるなかで、京都、チェンマイ、ジョグジャカルタにはいくつかの共通点が見られたと指摘します。
.jpg)
たとえば、どの都市にも数多くのアーティスト・スタジオが存在しています。また、いずれもかつては首都だった歴史ある都市です。そして、都市がコンパクトで地価も安いため、親密なコミュニティが形成されやすいという特徴もあります。
そこでこの3つの都市を念頭に、2部制で現代アートの「キャピタル(=首都)」について考えるシンポジウムが企画されることになりました。
第1部は「アジアにおける現代アート・キャピタル」と題して、チェンマイとジョグジャカルタのアートシーンを支えてきたプレイヤーたちによるプレゼンテーションを実施。トップバッターは、ジム・トンプソン・アートセンター(チェンマイ)ディレクターのクリッティヤー・カーウィーウォンが務めました。
都市から都市へと移ろうもの──チェンマイから名古屋まで
1964年にタイのチェンライで生まれたクリッティヤーは、進学を期にチェンマイに移り住みました。彼女に大きな影響を与えたのは、1990年代はじめにチェンマイではじまったパブリックアート・プロジェクトの「チェンマイ・ソーシャル・インスタレーション(CMSI)」。
.jpg)
チェンマイ大学の教授と地域のアーティストたちが主導したCMSIには、本シンポジウムの登壇者であるナウィン・ラワンチャイクンも参加していました。このプロジェクトは草の根的な運動であり、タイの現代アートの素地を整える重要な運動になったそうです。
一方のナウィンは、1971年にチェンマイで生まれたアーティストです。CMSIが始まる直前の1989年にチェンマイ大学美術学部に入学し、CMSIの中心人物でもあった教員のモンティエン・ブンマーと出会うことになりました。
1988年にパリ留学から帰国したばかりだったモンティエンは、アクリルやキャンバスなどの西洋的な画材を用いず、土、砂、灰、粘土などの非西洋的な素材で作品をつくっていたアーティスト/教育者です。1990年代のタイ美術界における「インフルエンサー」だったとナウィンは語ります。
モンティエンの影響のもと、ナウィンは学生だった1991年に最初の展覧会に参加することになりました。その際にアーティストのミット・ジャイインと知り合い、ミットとともにCMSIに参加したそうです。
先述したとおりCMSIはタイにおける現代アートを大きく前進させる運動になりましたが、チェンマイには継続的に作品を発表できるスペース不足という問題もありました。そこでナウィンはバンコクへ活動の幅を広げ、タクシーの内部をギャラリー空間に変えてしまう作品《ナウィン・ギャラリー・バンコク》などの発表を開始しました。
この作品はナウィンの出世作となり、タイが誇る国際的アーティストであるリクリット・ティラヴァーニャとのコラボレーションなど、ナウィンを世界の舞台に引き上げるきっかけになったそうです。
その後、ナウィンは「移動する都市」展(ヴィーン・ゼツェシオン館ほか)への参加など、世界各地で活躍するようになり、シドニー、ニューヨーク、東京、名古屋などで立て続けにプロジェクトを展開しました。
2000年には福岡に拠点を移し、インド系移民の子孫としての自身のルーツを顧みながら、日本におけるインド系コミュニティとのコラボレーションを開始。「あいちトリエンナーレ2010」では、名古屋にある長者町という繊維街とチェンマイを結びつける作品を発表しています。
チェンマイにはタイ・シルクの発祥地としての顔があり、今でも多くの町工場や問屋が立ち並んでいます。このように、異なる都市同士を結びつける活動はナウィンにとって重要で、都市から都市へ、あるいはコミュニティからコミュニティへと流動的に移ろいながら、ナウィンはアート活動を展開してきました。
アートよりも友達をつくること──ジョグジャカルタで見えてきたもの
1980年にジョグジャカルタで生まれたアリア・スワスティカは、現在ビエンナーレ・ジョグジャ(BJ)のディレクターを務めています。
アリアは、インドネシアで「サンガル」と呼ばれる伝統的なコミュニティの紹介からプレゼンを始めました。伝統的に舞踊や音楽のコミュニティとして機能してきたサンガルは、若い人々が集まり、新たな視点や思考を共有する場として機能しているそうです。
ジョグジャカルタでは、サンガルのように草の根的なコミュニティが重要な役割を果たしてきました。その影響力は美術館などの大きな施設にも勝るものだといいます。
たとえば、彼女がディレクションしているBJは、1988年に政府主導の絵画ビエンナーレとして始まった経緯があります。しかし1992年に若いアーティストからの抗議活動がおこり、絵画に限定されない国際芸術祭として1997年に再スタートすることになりました。
この運動を契機に、アーティストたちが公共空間で作品を制作・発表するようになりました。これはチェンマイで始まったCMSIともよく似た状況だったとアリアは語ります。
その一方で栗林隆は、アーティストの視点から「自身がジョグジャカルタに至った理由」を話してくれました。
日本の美大を卒業後、栗林は作家としての生き方を模索するため、1992年にカッセルに渡りました。カッセルは国際芸術祭「ドクメンタ」の開催地として知られるドイツの地方都市です。
12年間のドイツ生活を経て帰国した栗林は、2005年に神奈川県の逗子に拠点を移しました。逗子では、地域の人々が運営していた「シネマキャラバン」と出会い、ともに活動していたそうです。8年間の逗子生活ののち、さらなるコミュニティとの出会いを求めるべく、栗林はジョグジャカルタに移り住むことを決断しました。
初めてジョグジャカルタを訪れたときの印象は「豊かなコミュニティをもつ京都のような街だな」というものでした。移住後にインドネシアのアーティストたちと交流するなかで、現在カッセルで開催中の「ドクメンタ15」の芸術監督を務めている「ルアンルパ」とも知り合いました。
ルアンルパからの招待で、かつてカッセルで暮らしていた栗林はドクメンタに参加することになりましたが、その際に彼が受けたオーダーは「“アート”はつくらないでほしい」というものでした。
どういうことでしょうか? まず、ルアンルパは「ノー・アート、メイク・フレンズ(アートではなく、友達をつくろう)」を理念に活動しているアーティスト・コレクティブです。そんな彼らから見て栗林は、カッセル、逗子、ジョグジャカルタと各地の都市を転々としながら、「アートではなく、友達」をつくり続けてきた存在として共感できる相手だったのではないでしょうか。
そんなルアンルパからのオーダーに対して、栗林は「蚊帳の外」をテーマにしたプロジェクトで応答することにしました。
日本、中国、タイなどのアジア圏には「仲間はずれ」を意味する「蚊帳の外」という言葉があります。この言葉を逆手にとり、もともとはアートの外にいた人々──そのなかには栗林やルアンルパも含まれます──を「蚊帳の内」に招き入れる空間をつくることを思い立ったのです。これがルアンルパから受けた「アートではなく、友達をつくろう」というオーダーへの回答になりました。
ダイレクトに世界と繋がる京都の潜在力
以上のプレゼンに対して⼩崎哲哉(「Realkyoto Forum」編集長、京都芸術⼤学教授)より、京都、チェンマイ、ジョグジャカルタの3都市は「オルタナティブ」というキーワードで繋がるのではないかというコメントがなされました。
オルタナティブという言葉には「何かに取って代わるもの」という意味があります。たとえば、京都に対する東京のようにオルタナティブは何らかの対象を前提としているのです。

アートマーケットに目を向けてみると、今年、世界最大のアートフェアである「アート・バーゼル」には日本から30以上のコマーシャルギャラリーが出展しましたが、それらすべてが東京に拠点を置くギャラリーでした。
その一方で京都には数多くの大学が存在します。短大も含めると39校が京都にキャンパスを置き、京都市人口の約10分の1にあたる、15万人もの学生が在籍しているそうです。
アート・デザイン系の学生に焦点をあてれば、芸術系学部を有する一般大学も含めて、年間で2,000人もの卒業生が京都から輩出されています。
今年のヴェネツィア・ビエンナーレの日本館代表に選ばれたダムタイプのように、京都を拠点にしながら、東京を経由せずダイレクトに世界へ繋がるアーティストが増えてきました。
このように、従来「中心」として機能していた首都(=東京)を経由せず、これまでにはなかったプロセスで世界に繋がる潜在力が京都にはあるのではないでしょうか。
「移動する都市」展ができるまで
第2部では「潜在力」をテーマにしたディスカッションが行われました。登壇者は美術史家・キュレーター・批評家のサスキア・ボス、京都市京セラ美術館館長の青木淳、京都芸術センター館長の建畠晢、そして第1部にも登壇したクリッティヤーの4名、モデレーターは所長の浅田が務めました。
まず、京セラ美術館の館長で2020年に同館のリノベーションを担当した建築家でもある青木は、同館の歩みを振り返ることから京都という街が潜在的にもつ力について話しました。
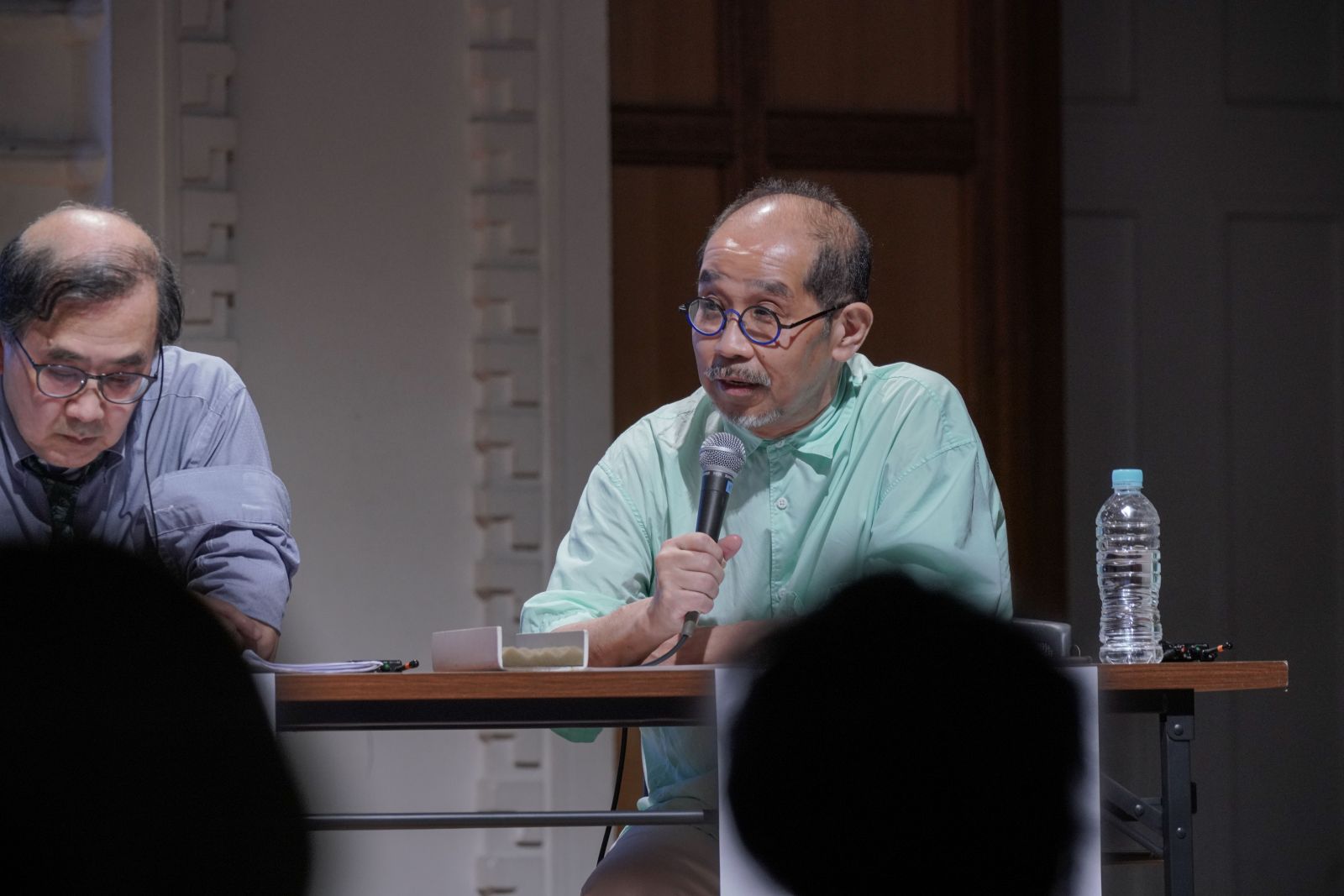
青木によると、1933年に開館した京都市美術館(現・京都市京セラ美術館)は、もともと京都の市民や財界の有力者たちの寄付によってつくられた美術館でした。そのため、同館は「町民がつくった美術館」といっても過言ではなく、リノベーションの際にも京都の人々へのリスペクトを込めて、できるだけもとの形を留めた改修をするように心がけたそうです。
それに対して建畠は、都市から都市への移動という観点から、第1部で話題にあがった「移動する都市」展について話しました。1997年にヴィーンの分離派会館で始まった同展は、東アジアにおける都市の変容をテーマとする展覧会でした。

キュレーションを手がけたのは、ハンス・ウルリッヒ・オブリストとホウ・ハンルの2人。オブリストは現在サーペンタイン・ギャラリーのディレクターを務めているキュレーターですが、自宅のキッチンで現代美術展を開催したり、オーストリア航空の機内で展覧会を開催したりするなど、独自の活動でも知られています。
一方のホウ・ハンルは、ポンピドゥー・センターで開かれた「大地の魔術師」展の開催中にパリを訪れていたところ、母国・中国で天安門事件が発生して帰国できなくなってしまい、フランス国籍を獲得することになったキュレーターです。
こうした2人が「移動」をテーマに展覧会をキュレーションしたことは、その背景を知るだけでも興味深い出来事だったと建畠は語ります。
それに対してサスキア・ボスは「移動する都市」展が開かれた前年にオブリストら複数人とともに初来日したエピソードを話してくれました。
北九州、東京、京都などを訪れたサスキアたちは、そのときの旅路はとても素晴らしいものだったと振り返ります。「移動する都市」展はボルドー、ニューヨーク、ロンドン、バンコク、ヘルシンキなど、世界各地を巡回しながら、それぞれの都市で新作を追加するなど、内容を大きく変容させた展覧会でした。こうした展示のあり方には、オブリストがサスキアたちと旅した東アジアでの経験が反映されていたのかもしれません。
相互批判はいかにして可能になるのか?
続いて、浅田から「コミュニケーション」にまつわる問題提起がなされました。日本の公立美術館では、学芸員の大半は日本人で、ほとんどすべての書類が日本語で作成されています。しかしこれまで見てきたように、アートには都市から都市へ、そして国から国へと流動的に接続しながら変容していく側面があります。
そこで日本の美術館の現状を好転させるために、浅田は第7回横浜トリエンナーレでアーティスティック・ディレクター選考委員長を務めた際、インド出身のラクス・メディア・コレクティヴをディレクターに選定したそうです。
このコメントに対して建畠は、多文化主義的な視点は疑いようがなく必要であるとした上で、異なる文化をもつ人々同士のコミュニケーションには誤解が付いて回り、それこそがコミュニケーションの重要な側面なのではないかと答えました。
建畠が一例に出すのはピカソです。かつてピカソがアフリカの仮面から影響を受けて作品をつくった際、果たしてその仮面がどの部族のもので、どういった用途のためにつくられたものなのかをピカソが知らなかったことに対し、文化剽窃ではないかと指摘する批判が存在します。
この批判に対して建畠は、もちろん他者の文化を知ろうとする努力は重要であるものの、他者の文化を完全に理解することもまた難しく、いかなるコミュニケーションも特定の文化や偏った視点に根ざしたものにならざるを得ない側面もあるのではないかと述べました。

このように、他者の文化を尊重しようとする多文化主義的な視点が生み出すジレンマに対して、ICA京都は「忌憚のない相互批判」を目指す場にしたいと浅田は語ります。
たとえば、もともとはアフリカ系アメリカ人の音楽だったジャズを白人が演奏することに対して「文化盗用(アプロプリエーション)である」とする批判があります。
「黒人の音楽は黒人にしかできない」という前提に立っているという点で、この批判には問題があると浅田は指摘します。その背景には「黒人には黒人の音楽がわかる」という認識があり、さらには「黒人女性には黒人女性にしかわからないことがある」「ハンディキャップをもった黒人女性には……」などとどこまでも細分化されてゆき、最終的には「私のことは私にしかわからない」というドグマにたどり着くことになるのです。
しかしその反面、「私には私のことがわからない」というパラドックスがあると浅田は述べます。たとえば、ある人から投げ掛けられた言葉に必死で応答したときに「私はこんなことを考えていたのか」と再認識することがあるように、アフリカ系アメリカ人にとってのジャズも、他者から「ジャズはすごい」と言われたときに初めて自身がジャズの魅力を発見できるというプロセスがコミュニケーションの前提にあるからです。
この議論に対してサスキアは「コラボレーションこそが重要な答えになる」と応答しました。彼女のいうコラボレーションは、従来的な協働や共演のようなものだけでなく、より広い意味のものであり、たとえば本シンポジウムもすでにそのひとつであるといいます。
実際に彼女はこれまでに世界各地で「コラボレーション」を積み重ねており、中には編集者とアートマガジンの制作に取り組んだ事例もあったそうです。
他者の文化を理解するためには、まずはお互いの思考を共有することこそが重要であり、そのうえで本当の意味での「相互批判」が可能になるのではないかとサスキアは語りました。
こうした一連の議論に対して、最後に浅田から「ICA京都ではこれからもチェンマイやジョグジャカルタとリレーするようなコラボレーションを目指しつつ、最終的には日本のアート・ワールド全体が変わっていくようなネットワークの広がる夢を抱いていきたい」とコメントし、盛会のうちにシンポジウムが締め括られました。
(文:藤生新、撮影:吉見崚)
京都芸術大学 Newsletter
京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。
-
京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts
所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス
連絡先: 075-791-9112
E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp






